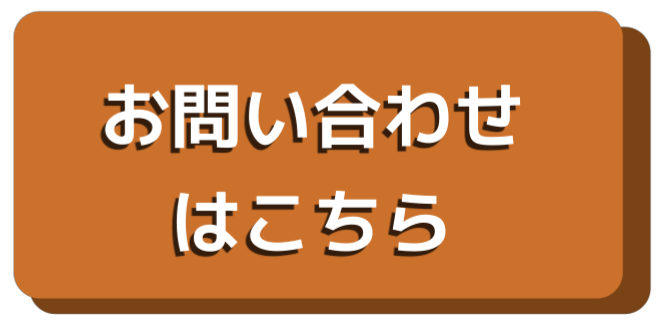離婚後の住宅ローンはどうなる?トラブルを回避するための方法をご紹介

離婚の際、最も複雑でトラブルになりやすいのが「住宅ローンの残る家」の扱いです。
夫婦で築いたマイホームには、思い出と同時にローン・登記・保証といった法的な関係が複雑に絡んでいます。
「家の名義は夫だけど、妻もローンを払っていた」
「妻と子どもが住み続けたいけれど、ローンは夫のまま」
こうした状況は非常に多く見られます。
離婚をすれば婚姻関係は解消されますが、住宅ローン契約は銀行との法律上の契約であり、離婚によって自動的に消えることはありません。
また、家を残す・売る・引き継ぐなどの選択次第で、今後の生活や信用情報にも大きな影響が出ます。
この記事では、弁護士の視点から離婚後の住宅ローンの取り扱いをわかりやすく整理し、実際にトラブルを防ぐための具体的な方法を紹介します。
離婚と住宅ローンの関係を整理しよう
まず理解しておきたいのは、住宅ローンが残っている家も財産分与の対象になるという点です。
住宅ローンの残高があっても、その家が「婚姻期間中に取得したもの」であれば、共有財産として取り扱われます。
ただし、実際の取り扱いは次のようにパターン分けされます。
| 所有形態 | 支払者 |
|---|---|
| 夫単独名義でローン契約も夫 | 最も一般的。離婚してもローンは夫の責任で支払い継続。 |
| 夫婦の共有名義(連帯債務) | 離婚後も両者に支払い義務が残る。どちらかが滞納すれば、もう一方に請求が及ぶ。 |
| 片方が借入人でもう一方が連帯保証人(またはペアローン) | 保証人であっても、主たる債務者が払えなければ、全額の支払い義務を負う。 |
離婚後、これらの契約関係は自動的に解除されません。
そのため、「離婚後も元配偶者とローンでつながっている」状態が続く場合があります。
このまま放置すると、相手の滞納で信用情報に傷がつくなど、深刻な問題に発展することがあります。
名義・ローン・居住のパターン別に見る注意点
住宅ローンを抱えたまま離婚する際は、「名義」「ローン」「居住」の3つの関係を明確に切り離して考えることが大切です。
(1)夫名義・ローン契約者、妻と子が住み続けるケース
もっとも多いのがこのパターンです。ケース分けして説明します。
【ケース①】夫がローンを払い続け、妻と子が無償で住み続ける(使用貸借)
もっとも一般的なケース。
離婚協議で「夫が支払いを継続」「妻と子が居住を続ける」と合意する形。
リスク:夫が支払いを止めれば、銀行は競売に踏み切れる。
妻と子に所有権も居住権もなく、強制退去になることもある。
対策:離婚協議書で「支払いが滞った場合の扱い」を明記。
妻が自立後、早期に別居・借り換えを検討。
滞納が判明したら、銀行に「任意売却」の相談を行う。
妻が住み続けたい場合は、第三者(親族・再婚相手)による買取+賃貸化も検討。
またローン規約に違反する可能性あり。
【ケース②】夫がローンを払い続け、妻が「家賃」を支払う(賃貸借契約)
妻と子が夫名義の家に住み続ける代わりに、一定額の家賃を支払う形式。
メリット:金銭関係が明確になり、トラブル防止につながる。
デメリット:妻の支払った家賃はローン返済には充てられない(あくまで夫の収入扱い)。
長期的には妻側の負担が重くなりやすい。またローン規約に違反する可能性あり。
対策:賃貸借契約書を作成(期間・金額・更新条件を明記)。
実質的に財産分与・慰謝料の代替にならないように注意。
【ケース③】夫から妻へ家を譲渡し、妻がローンを引き継ぐ(名義変更+借り換え)
実務上は「最も望ましい」形だが、金融機関の審査を通ることが前提。
妻が単独で安定した収入を得ている場合に限り、ローンの借り換えを認める銀行もある。
メリット:所有権と返済義務を一致させ、後のトラブルを根絶できる。
デメリット:銀行の審査が、非正規雇用・専業主婦では承認されにくい。
不動産の持分移転に伴う税金(登録免許税・贈与税)の検討も必要。
対策:司法書士にも依頼し、名義変更と借り換え契約を同時に進行。
金融機関の「団体信用生命保険(団信)」条件の見直しも忘れずに。
(2)夫婦の共有名義(連帯債務)のケース
この場合、離婚しても両者に返済義務が残ります。
片方が支払わなくなれば、もう一方が全額負担する義務を負うため、離婚後もローンによる経済的つながりが続くという点に注意が必要です。
実務上は、「家を売却して残債を清算する」または「どちらか一方がローンを引き継ぐ」形が一般的です。
(3)妻名義・夫が連帯保証人のケース
保証人となっている夫は、離婚後も支払い責任を免れません。
仮に妻が返済不能になれば、銀行は保証人である夫に請求します。
保証契約を解除するには、金融機関の同意が必要であり、離婚届を提出しただけでは法的効果はありません。
離婚時に選ぶべき3つの選択肢
離婚後の住宅ローンをどう整理するかは、生活の安定を左右する重要な決断です。
大きく分けて、次の3つの選択肢があります。
(1)家を売却してローンを完済する
もっともシンプルでトラブルの少ない方法です。
家を売却し、その代金でローンを完済すれば、契約関係を完全に断ち切ることができます。
残債が残る場合は「任意売却(銀行の同意を得て売却)」という手段を取ることも可能です。
ただし、売却価格が残債を下回ると債務が残るため、事前に査定と返済計画を確認しておくことが大切です。
(2)どちらか一方が家とローンを引き継ぐ
夫婦のどちらかが住み続ける場合、銀行の審査を経て単独名義でローンを組み直す(借り換え)方法があります。
ただし、単独で支払い能力が認められない場合は難しく、現実的には拒否されるケースも多いのが実情です。
離婚後の収入・職業・年齢など、あらゆる条件を見直して判断する必要があります。
(3)名義人は夫のまま、妻と子が住み続ける(使用貸借)
この方法は感情的に選ばれやすいですが、法的には非常に不安定です。
夫の支払いが滞れば、銀行が競売を実施し、家を失うおそれがあります。
使用期間・固定資産税の負担・退去条件などを離婚協議書に明記しておくことが最低限の備えになります。
離婚協議書・公正証書で決めておくべき内容
住宅ローンと家の扱いは、離婚後に最も揉めやすい問題の一つです。
感情的な話し合いではなく、法的に有効な書面(離婚協議書・公正証書)で取り決めを残すことが不可欠です。
(1)離婚協議書に記載すべき項目
以下のような内容は、必ず明文化しておく必要があります。
家の所有権・居住権の扱い
例:「家の名義を夫とし、妻および子が当面の間居住することを認める」
ローンの返済者・負担割合
例:「住宅ローンは夫が全額支払い、滞納があった場合は妻の居住権を失う」
固定資産税・修繕費・保険料の負担
どちらが支払うか明確にしておく。
将来の売却条件・代金分配方法
将来売却したときに、売却益や残債をどう処理するかを明確にしておく。
こうした文言を曖昧にしたまま離婚してしまうと、数年後にトラブルが再燃するケースが少なくありません。
(2)公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書にしておくことで、ローン支払いなど金銭債務に強制執行力が生じます。※但し、定め方に工夫が必要です。
つまり、相手が約束を守らなかった場合、裁判を起こさずに差押え手続きが可能になるのです。
住宅ローンが関係する取り決めは金額も大きく、「口約束」や「LINEでの合意」では法的に無効に近いため、専門家のサポートが不可欠です。
よくあるトラブル事例と回避策
住宅ローン問題では、離婚後に次のようなトラブルが頻発します。
(1)夫名義ローンの滞納で妻子が立ち退きに
(2)連帯保証人のまま離婚して債務請求を受けた
(3)「家をそのままにして離婚」した結果、相続トラブルに発展
(4)住宅の名義を変えたのに登記を放置
こうしたトラブルの多くは、離婚時に正しい法的整理を行っていないことが原因です。
一度ローンを組んだ家は、「所有」「債務」「居住」の3つを分けて考え、契約と書面で固定しておくことが重要です。
こういったことを踏まえ、下記では、弁護士に依頼するメリットを紹介します。
弁護士に相談するメリット
住宅ローン付き不動産の離婚問題は、法律と金融の両方を理解していなければ正確に整理できません。
弁護士に依頼することで、次のような具体的なサポートを受けることができます。
(1)離婚協議書・公正証書の作成
ローン・固定資産税・登記など複数の要素を含む場合、一般的なテンプレートでは対応できません。
弁護士が関与すれば、実際のローン契約内容を反映した有効な条項を作成できます。
⑵不動産・税金・債務整理まで一括対応
P&M法律事務所では、司法書士・税理士・不動産業者と連携し、
「売却」「名義変更」「残債整理」までワンストップで対応可能。
離婚後の生活再建を見据えた実務的な解決策を提案します。
まとめ「感情ではなく「契約」で安心を守る」
離婚後の住宅ローン問題は、感情論で進めると必ず後でトラブルになります。
ローン契約は銀行との法的約束であり、離婚しても消えません。そのため、書面での取り決めと専門家による確認が不可欠です。家を残す・売る・引き継ぐ――どの選択を取るにしても、「誰が所有し」「誰が返済し」「誰が住むのか」を明確にしておくことが、最も重要なトラブル回避策です。
住宅ローン問題は、単にお金の問題ではありません。
家には「家族の記憶」「子どもの成長の記録」が詰まっているため、離婚時に家を手放すかどうかの判断は、多くの人にとって精神的に非常に重い決断となります。
そのため、「住み続けたい」「子どもを転校させたくない」という感情から、現実的に支払いが困難なプランを選んでしまうケースも少なくありません。弁護士は、冷静に数字を整理し、将来の生活設計を一緒に考えることで、感情に左右されない最善の判断を支援します。
P&M法律事務所では、住宅ローン・財産分与・離婚協議書の作成など、複雑な離婚問題に幅広く対応しています。
離婚後の生活を安定させたい方、住宅ローンに不安を感じている方は、ぜひ早めにご相談ください。法的な整理と将来の見通しを両立させ、安心して新しい生活を始めるためのお手伝いをいたします。

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」
関連記事
-

離婚後の住宅ローンはどうなる?トラブルを回避するための方法をご紹介
-


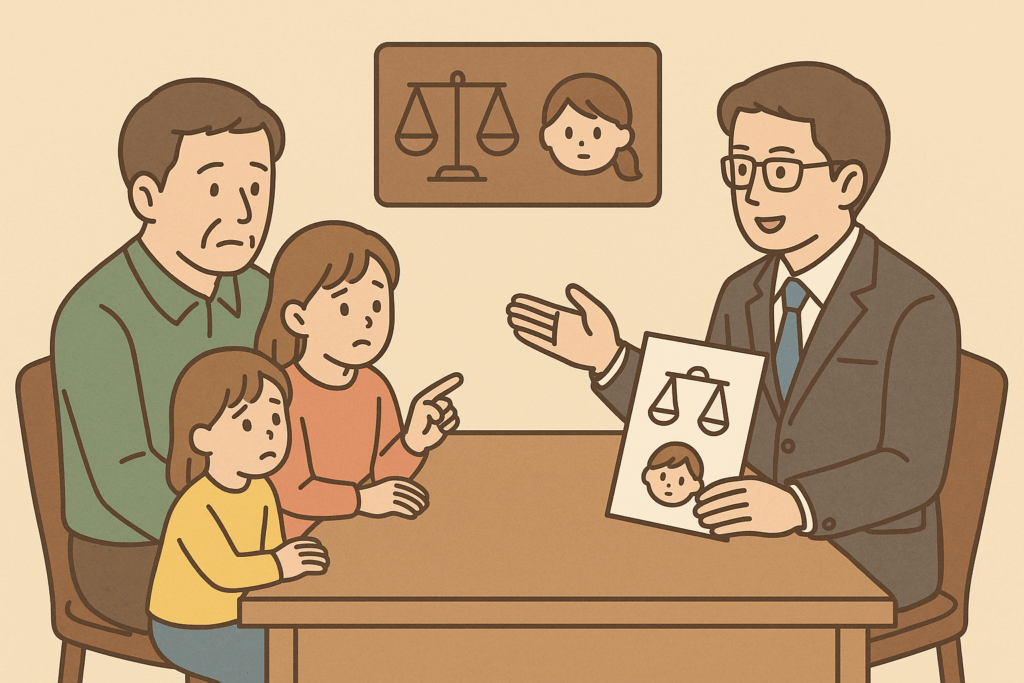
離婚時の親権はどうなる?親権者の決め方や注意点を離婚に強い弁護士が解説
-


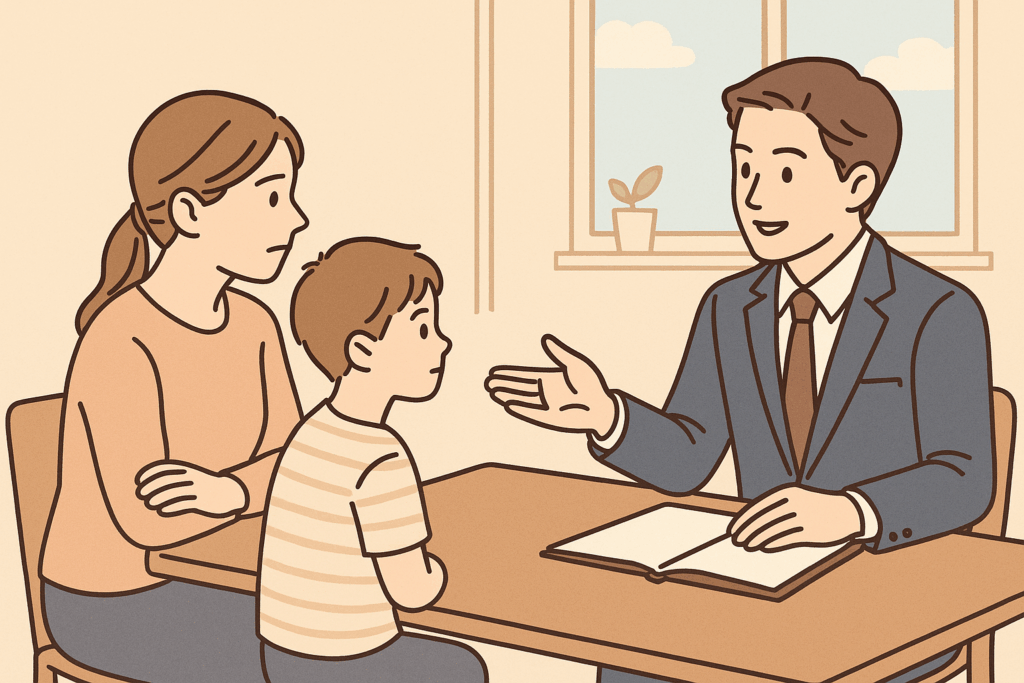
離婚時に定める養育費とは?相場から請求方法の流れまで分かりやすく解説
-


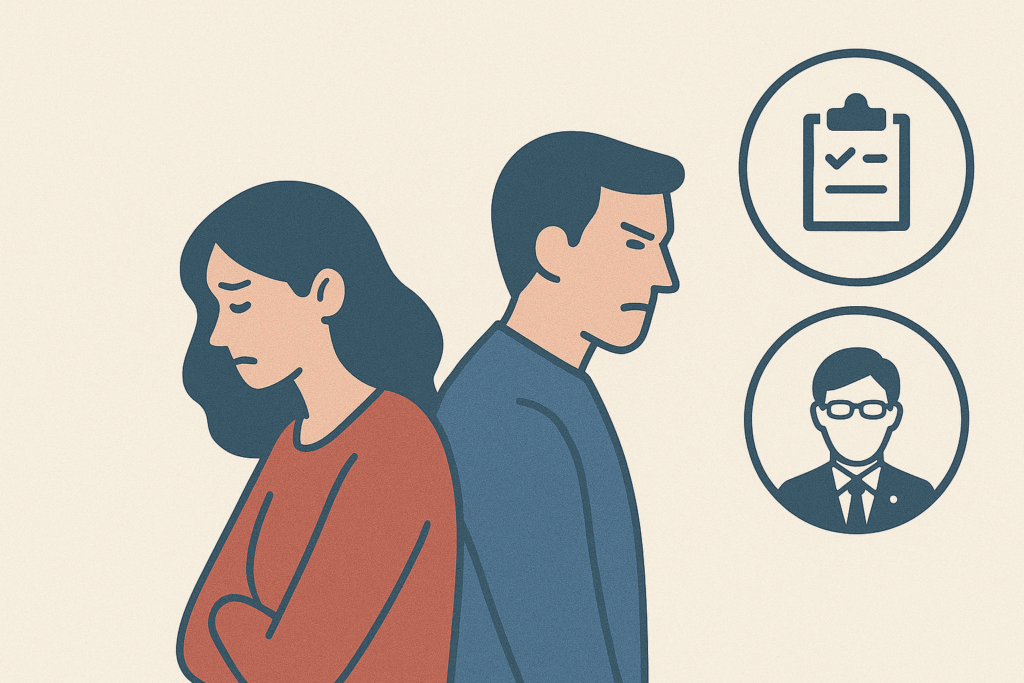
離婚調停とは?申立ての流れや費用・気を付けるポイントまで弁護士が解説
-



婚姻費用を請求されたら?支払い義務と決定後の減額交渉のポイント
-



不貞行為はどこから?離婚事由、慰謝料が発生するケースも紹介!
-


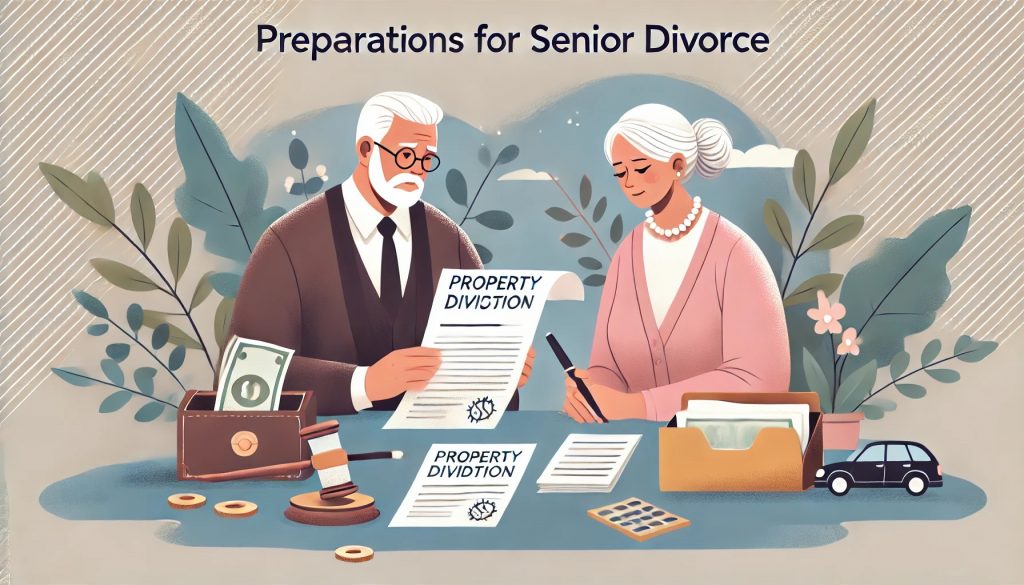
熟年離婚を思い立ったら読む記事
-



増え続ける熟年離婚、考えておくべきポイント・注意点
-



離婚の慰謝料の相場とは?弁護士に相談したほうがいい場合も解説!
-


に向けて別居前にすべき7つのこと-1024x576.jpg)
高所得者との離婚(財産分与)に向けて別居前にすべき7つのこと
-



離婚に際して財産分与をする場合~隠し財産の探し方~
-



離婚後の相続について解説!子供の相続や困った場合の相談先を紹介