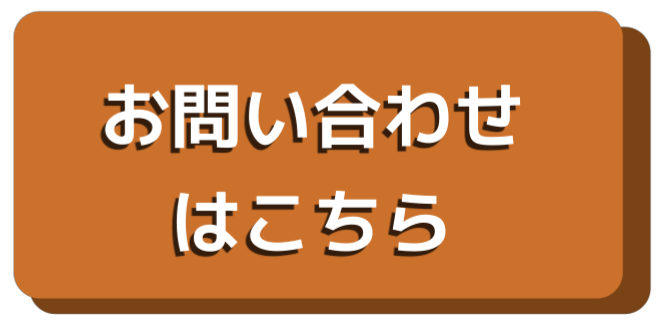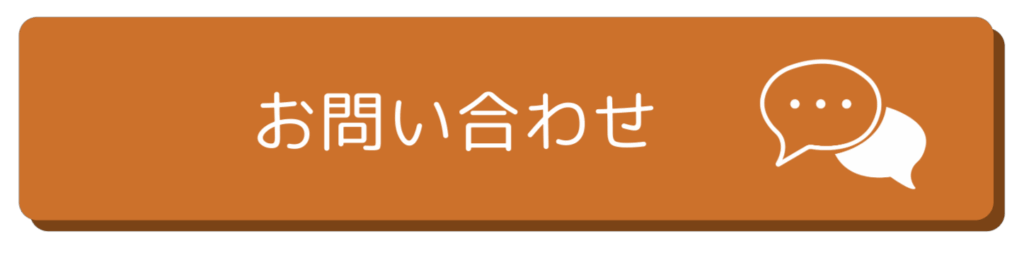離婚時の親権はどうなる?親権者の決め方や注意点を離婚に強い弁護士が解説

離婚の際、最も感情的な対立を生みやすいのが「子どもの親権」です。
どちらが親権を持つかは、単に「どちらの親がふさわしいか」ではなく、子どもにとって最善の利益がどこにあるかという観点で判断されます。
しかし、現実には「母親が有利なのでは?」「収入が少ないと不利になるのか?」など、誤解や不安の多いテーマでもあります。
この記事では、離婚・親権問題に詳しい弁護士が、親権の基礎から判断基準、手続きの流れまでを実務に即してわかりやすく解説します。
なお、2026年4月1日から改正民法で共同親権導入される予定です。但し、共同親権が導入されても、本記事に書いてあることが、親権者を決める上で重要であることには変わりありません。
親権とは?監護権との違いを正しく理解しよう
「親権」とは、未成年の子どもを育てる親の権利と義務をまとめたもので、法律上は民法820条ほかに定められています。
親権には、大きく分けて次の二つの内容があります。
身上監護権:子どもの生活・教育・居所を決める権限
財産管理権:子どもの財産を管理し、法律行為の代理を行う権限
親権の目的は親の権利を守ることではなく、子どもの健全な成長を守ることにあります。
そのため、親権を持つ親には、教育・医療・進学など、あらゆる面で子どもの利益を優先して判断する責任が生じます。
一方で、しばしば混同されるのが「監護権」です。
監護権とは、子どもを実際に世話し、日常生活を共にする権限を指します。
簡単に言えば、「親権=法律上の権限」、「監護権=日常生活の世話」と理解するとわかりやすいでしょう。
離婚後は、親権者をどちらか一方に決めなければなりません(民法819条1項)。
今のところ原則として共同親権は認められていませんが、例外的に「親権者=父」「監護権者=母」と分ける取り決めも可能です。
ただし実務上は、子どもを実際に養育している側(監護している側)が親権者となるケースが圧倒的に多く見られます。
親権者を決めるタイミングと方法
離婚をする際には、必ず親権者を決めておかなければ離婚届が受理されません。
つまり、親権をめぐる話し合いがまとまらない限り、協議離婚は成立しないのです。
親権の決め方は、離婚の方法によって次の3つに分かれます。
(1)協議離婚の場合
夫婦間で話し合いにより親権者を決めます。
どちらが親権を持つか、また監護権を分けるかどうかも自由に合意できます。
ただし、感情的な話し合いではなく、子どもの生活環境を基準に冷静に判断することが重要です。
(2)調停離婚の場合
協議で合意できない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
調停委員が双方の意見を聞き取り、合意形成をサポートします。
合意が成立すると「調停調書」が作成され、裁判の判決と同じ効力を持ちます。
(3)裁判離婚の場合
調停が不成立となった場合、裁判所が最終的に親権者を決定します。
この際、裁判所は「子どもの利益」を最も重視し、生活実態・監護環境・心理的安定などを総合的に考慮して判断します。
親権の取り決めは、離婚届の「親権者欄」に記載されます。
この欄が未記入だと離婚は成立しないため、必ず明確に決めておく必要があります。
裁判所が親権を判断する基準とは
親権を争う際、家庭裁判所は「子どもの福祉」を最優先に判断します。
この「福祉」とは単なる経済力や愛情の深さではなく、子どもが安定した環境で心身ともに成長できるかという観点です。
裁判所が考慮する主な判断基準は次のとおりです。
(1)監護の継続性
現在どちらが子どもを育てているかは極めて重要な要素です。
別居後、継続して子どもと生活している親の方が「子の安定性」を保ちやすいと判断される傾向にあります。
(2)養育環境
経済力だけでなく、住居の安定性・生活リズム・親族のサポート体制などが重視されます。「高収入だから有利」という単純な話ではなく、子どもが落ち着いて生活できるかが基準です。
(3)子どもとの愛着関係
乳幼児の場合は、一般的に母親との心理的結びつきが強く見られる傾向にあります。
一方で、学齢期以降の子どもでは、親子の信頼関係や情緒的な安定が判断材料となります。
(4)子どもの意思
15歳以上の子どもがいる場合、家庭裁判所は本人の意見を聞き取ります(家事事件手続法169条)。ただし、子どもの意見が絶対ではなく、あくまで他の事情と総合的に判断されます。
(5)DV・虐待・精神状態などの安全性
暴力・アルコール依存・精神疾患など、監護能力に疑問がある場合は厳しく審査されます。
子どもへの安全確保は最優先事項であり、これらの要素が確認されると親権取得は極めて困難になります。
このように、裁判所は一方の親を敵視するのではなく、「子どもの生活の安定をどちらがより確保できるか」を冷静に判断しています。
弁護士は、これらの基準を踏まえて客観的な証拠を整理し、説得的な主張を行う役割を担います。
親権を争う場合の手続きと注意点
親権をめぐる話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判を経て決定されます。感情的な対立が深くなりやすいため、冷静な法的手続きで進めることが重要です。
(1)調停による話し合い
「親権者指定調停」または「離婚調停」の中で親権について協議します。
調停委員(男女各1名)が双方の主張を整理し、合意点を探ります。
合意に至れば「調停調書」が作成され、これは判決と同じ効力を持ちます。
調停では、どちらが現在子どもを養育しているか、今後安定した生活を維持できるかを中心に話し合われます。
たとえば「子どもの生活リズム」「保育園・学校の環境」「祖父母の支援」など、生活実態を具体的に説明することが求められます。
(2)審判・裁判による決定
調停で合意できない場合、家庭裁判所の「審判」または離婚訴訟の中で裁判官が親権者を指定します。
この際、家庭裁判所調査官が家庭訪問や聞き取り調査を行い、子どもの生活環境を客観的に確認します。
裁判官はその報告書をもとに、「子どもの福祉」に最もかなう形で判断します。
(3)実務で注意すべきポイント
親権をめぐる争いでは、「子どもを自分のもとに置くために突然連れ出す」といった行動は極めて危険です。
無断で子どもを移動させた場合、「違法な連れ去り」として親権判断に不利に働くおそれがあります。
また、相手への誹謗中傷やSNS投稿も、家庭裁判所での印象を悪化させる原因になります。
親権を得たい場合は、弁護士を通じて法的に適切な手段を選び、証拠を整理して進めることが不可欠です。
親権を得るために意識すべきポイント
親権を得るために重要なのは、「どちらの親がより子どもの幸せを守れるか」を客観的に示すことです。
裁判所は愛情の深さよりも、継続的・安定的に子どもを養育できる環境が整っているかを重視します。
以下では、実務で評価される具体的なポイントを解説します。
(1)安定した生活環境を確保する
最も重視されるのが「子どもが安心して生活できる環境が整っているか」です。
そのため、住居が安定しており、転居の予定がないことは大きな強みになります。
職業・収入が安定していることももちろん重要ですが、「勤務時間が極端に長く、育児時間が取れない」という場合は不利に評価されることもあります。
たとえ収入が高くても、子どもが放置されるような環境では“福祉に反する”と判断されるのです。
また、祖父母などの協力体制もプラスに評価されます。
実際の裁判例でも、「母方祖父母と同居し、日常的に子どもの面倒を見ている」という事実が、安定した養育環境として重視されたケースが多く見られます。
(2)監護の継続性と育児実績
裁判所は、現在子どもを実際に監護している親を優先する傾向があります。
別居後も一貫して子どもの世話・学校対応・医療管理を行っているかが重要です。
このため、別居前から「自分がどれだけ育児に関わっていたか」を証拠で示せるよう、生活記録を残すことが効果的です。
たとえば、以下のような記録は有力な資料になります。
・保育園・学校への連絡帳、担任とのやり取り
・通院・予防接種の記録、病院の領収書
・食事・遊び・通学など日常生活の写真
・家計簿や日記など生活実態を示す書類
裁判所は、こうした客観的証拠をもとに「どちらが安定して養育しているか」を判断します。
(3)子どもとの心理的つながりを保つ
親権は単に“経済的に育てられるか”ではなく、子どもが精神的に安心して過ごせるかも大切な要素です。
別居中であっても、面会交流を継続している親は「愛着関係を維持している」と評価されやすくなります。
反対に、感情的な対立から面会を拒絶すると「子どもの福祉を損なう行為」と見なされ、不利になることもあります。
裁判所は、面会交流を円滑に行える親を「より柔軟で子どもの利益を優先できる親」として高く評価します。
したがって、相手方との関係が悪化していても、冷静に対応することが重要です。
(4)感情的にならず冷静に行動する
親権争いでは、SNSへの投稿や感情的なメールが証拠として提出されることがあります。
「相手を非難する発言」「子どもを利用した圧力行為」などは、家庭裁判所で非常に不利に働きます。
裁判所は「子どもに悪影響を与えない親」を選ぶ傾向があるため、常に冷静な対応を心がけることが欠かせません。
また、調停や裁判の場では、発言内容や態度が調停委員・裁判官の印象に大きく影響します。
弁護士が同席していれば、発言の整理やトーンの調整を行ってくれるため、感情的にならずに手続きを進めることができます。
(5)別居時の対応が親権判断に直結する
別居の際に「子どもを連れて出た」または「置いて出た」という行動が、その後の親権判断に影響するケースが多くあります。
家庭裁判所は、別居時に子どもを継続して監護している側を重視するため、別居前後の行動は慎重に計画すべきです。
無理に子どもを連れ去るような行為は「監護の安定を乱す」と判断され、かえって不利になります。
別居を検討している段階から弁護士に相談し、適法かつ安全な形で監護権を確保する戦略を立てることが、後の親権争いを有利に進めるカギです。
(6)子どもの成長段階に応じた配慮
乳幼児期は母親が有利とされがちですが、最近の裁判実務では「父親の育児参加」「働きながらの共同養育」も評価されています。
一方で、学齢期以降では、子どもの意向・友人関係・学校環境などが重視される傾向にあります。
そのため、「子どもが今の環境で落ち着いて暮らせるか」を中心に主張を組み立てることが大切です。
弁護士が関与すれば、裁判例や調査官の判断傾向を踏まえて、どの要素を強調すべきかを戦略的に整理できます。
弁護士に相談するメリット
親権をめぐる争いは、感情だけで進めると長期化し、結果的に子どもに負担を与えることがあります。
弁護士に依頼することで、冷静かつ戦略的に対応することが可能になります。
(1)法的な整理と証拠の選定
弁護士は、裁判所の判断基準を踏まえて必要な資料(収入証明・学校記録・家庭写真など)を整理します。
これにより、主張に一貫性を持たせ、説得力を高めることができます。
(2)調停・審判での代理対応
家庭裁判所でのやり取りは専門的で、感情的になりやすい場面も多いです。
弁護士が代理人として出席すれば、冷静な交渉ができるだけでなく、調停委員や裁判官に正確に意見を伝えることができます。
(3)心理的サポートと長期的視点
親権問題は「子どもの利益」という正解のないテーマです。
P&M法律事務所では、法的支援だけでなく、依頼者の心理的ケアも重視し、子どもの将来を見据えた現実的な解決策を提案しています。
まとめ
親権は、どちらの親が勝つかを決める争いではありません。
「子どもが最も安定して暮らせる環境を整えること」こそが本質です。
そのためには、感情を抑え、法的手続を理解し、的確に準備することが欠かせません。
離婚や親権に関する問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
P&M法律事務所では、親権・監護権・養育費など、家族法全般に精通した弁護士が、あなたとお子さまの未来を守るために全力でサポートいたします。
関連記事
-

離婚後の住宅ローンはどうなる?トラブルを回避するための方法をご紹介
-


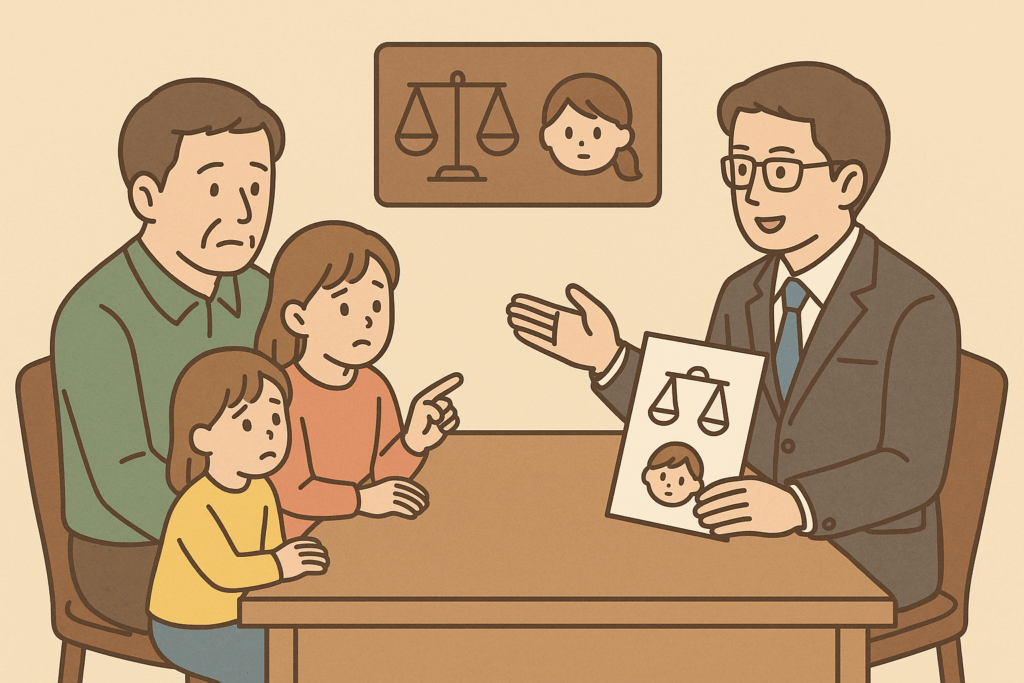
離婚時の親権はどうなる?親権者の決め方や注意点を離婚に強い弁護士が解説
-


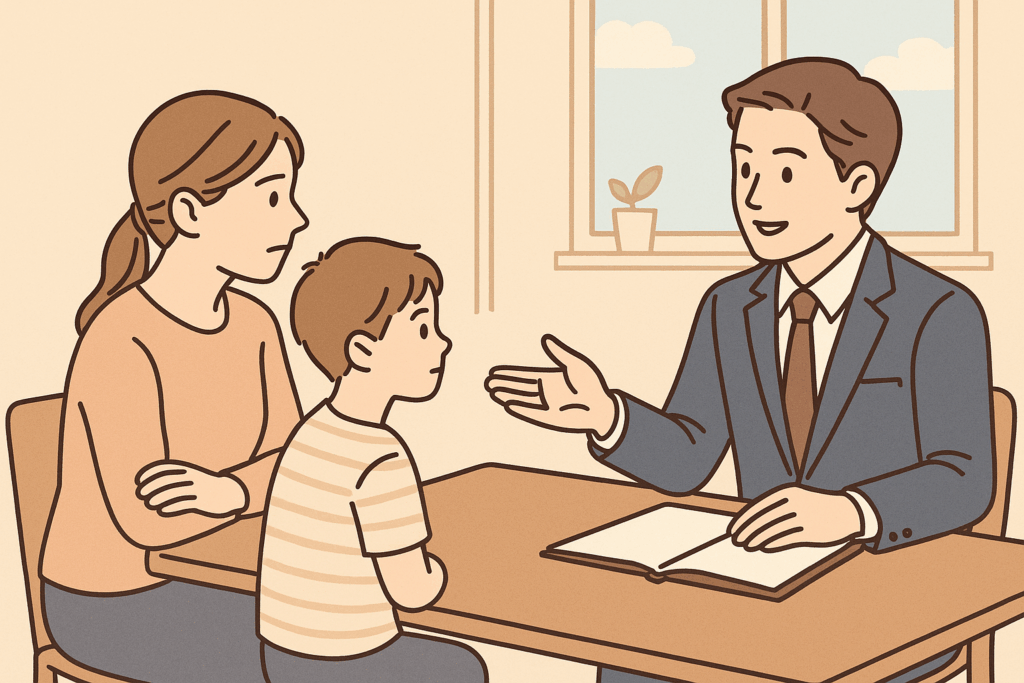
離婚時に定める養育費とは?相場から請求方法の流れまで分かりやすく解説
-


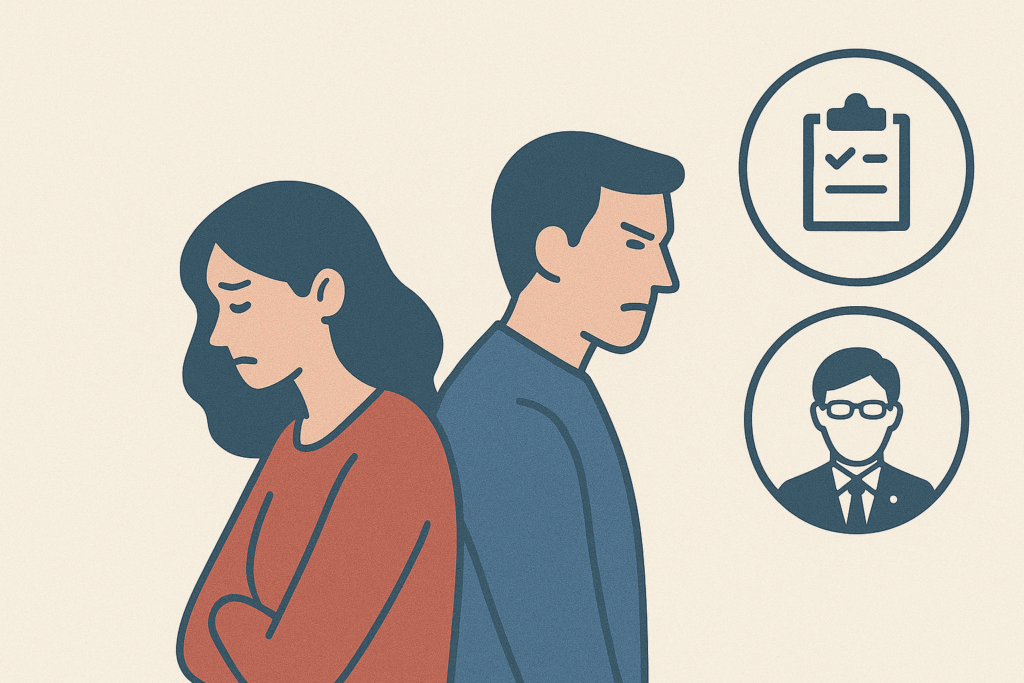
離婚調停とは?申立ての流れや費用・気を付けるポイントまで弁護士が解説
-



婚姻費用を請求されたら?支払い義務と決定後の減額交渉のポイント
-



不貞行為はどこから?離婚事由、慰謝料が発生するケースも紹介!
-


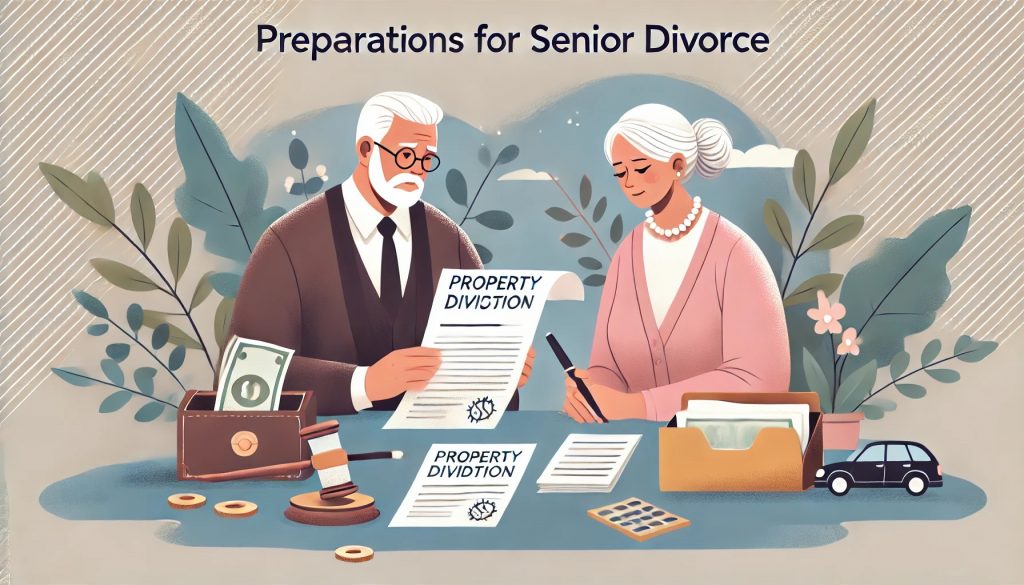
熟年離婚を思い立ったら読む記事
-



増え続ける熟年離婚、考えておくべきポイント・注意点
-



離婚の慰謝料の相場とは?弁護士に相談したほうがいい場合も解説!
-


に向けて別居前にすべき7つのこと-1024x576.jpg)
高所得者との離婚(財産分与)に向けて別居前にすべき7つのこと
-



離婚に際して財産分与をする場合~隠し財産の探し方~
-



離婚後の相続について解説!子供の相続や困った場合の相談先を紹介


P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」