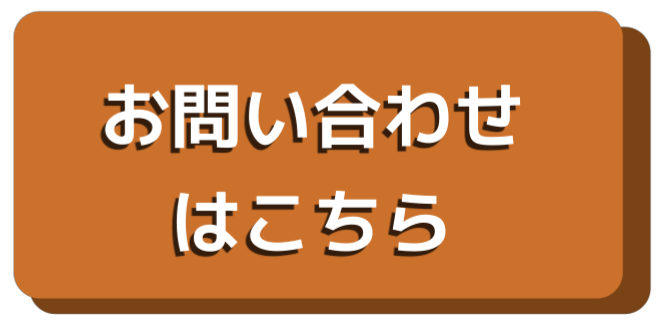離婚時に定める養育費とは?相場から請求方法の流れまで分かりやすく解説

離婚という大きな決断のあとに、「子どもの生活をどう守るか」という問題を抱える方は多くいらっしゃいます。
とくに、子どもの衣食住や教育、医療にかかる費用は、どちらか一方の親だけで負担するには重くのしかかることがあります。
このような中で、子どもが経済的に困ることなく健やかに成長できるようにする制度が「養育費」です。養育費は、離婚した後も親としての責任を果たすために不可欠な仕組みであり、法的にも明確に義務づけられています。
しかし実際には、「いくら支払うのが妥当なのか」「いつまで支払う必要があるのか」「相手が払わなくなったらどうすればいいのか」といった疑問や不安を抱く方が非常に多いのが現実です。
養育費を取り巻く現状
養育費を取り決めたにもかかわらず、離婚後に支払いが途絶えてしまうケースも少なくありません。
厚生労働省の調査によると、養育費を「取り決めている」と回答した母子家庭は約50%に満たず、実際に「現在も受給している」と答えたのは30%にも及びません。つまり、多くの家庭で養育費が十分に支払われていない現状があるのです。
厚生労働省,2022,「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」,(2025年10月20日取得,参考資料4_令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果)
この問題の背景には、
・養育費の金額を正しく計算していない
・書面で法的拘束力のある形にしていない
・相手が支払わなくなったときの対処法を知らない
といった手続面での知識不足も関係していると思われます。(相手に支払い能力がない、等そもそも支払いを受けられないという可能性もありますが、本記事では、そういった場合を除き、法的な解決を目指せる場合の解説を主目的といたします。すべての子どもに必要な費用が行き渡ることを願ってやみません。)
本記事では、こうした不安や疑問を解消するために、弁護士の視点から養育費の基礎知識から実務の流れまでをわかりやすく解説します。
相場の考え方、請求の方法、支払いが止まったときの対処法、さらには弁護士に依頼するメリットまで、実際の事例を交えながら丁寧に説明していきます。
離婚後の新しい生活を安心して始めるために、まずは養育費の仕組みを正しく理解することから始めましょう。きちんと制度を知り、正しい形で取り決めをしておくことが、お子さまの未来を守る第一歩となります。
養育費を定める意味と重要性
離婚は夫婦の関係を終わらせる手続きですが、子どもにとっては親であることに変わりはありません。
離婚後も、子どもが健やかに成長するために必要な生活費・教育費を負担し続けることが、親の法的かつ道義的な義務とされています。
その費用を「養育費」と呼びます。
養育費をきちんと取り決めておかないと、離婚後に生活費の不足が発生し、子どもの進学や医療に支障をきたすこともあります。
一方で、支払う側も「どの程度の金額が妥当なのか」を把握していないと、過大・過小な負担をめぐって再びトラブルになる可能性があります。
そのため、離婚時には双方が納得できる金額と支払方法を明確に定めることが極めて重要です。
また、養育費の取り決めは「口約束」だけでは法的拘束力が弱く、支払いが滞った際に強制執行できないという問題があります。
そのため、公正証書や家庭裁判所の調停調書として残すことが推奨されています。これにより、支払いが滞った場合でも強制的に回収することが可能となります。
養育費とは?対象となる費用の範囲
養育費という言葉はよく耳にしますが、その中身を正確に理解している人は意外に少ないものです。
養育費とは、未成熟の子どもが社会的・経済的に自立できるまでの間に必要となる費用を指します。
主な内訳は以下のとおりです。
生活費:衣食住、光熱費、日用品費など
教育費:授業料、教材費、塾や習い事の費用など
医療費:通院費や治療費、保険適用外の医療費など
その他:交通費、通信費、学校行事費など
子どもが高校や大学に進学する場合には教育費が大きな割合を占めるため、将来を見越した取り決めが必要です。
また、養育費の支払い義務は「成人年齢」ではなく「社会的自立」を基準に判断されるため、大学進学が一般的な現代では22歳(大学卒業時)ごろまで支払いが継続するケースも珍しくありません。
なお、養育費は子どものためのものであり、親同士の感情的な対立とは切り離して考えるべきです。支払う側にとっても、子どもの健やかな成長を支える重要な責任です。
養育費の金額(相場)の考え方と計算方法
養育費の金額は、法律で一律に定められているわけではありません。
一般的には、両親の年収や子どもの人数・年齢などを基準に「家庭裁判所が公表する算定表」をもとに決められます。
算定表とは
算定表とは、最高裁判所の司法研修所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」を指します。
裁判所(2018)『平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について』平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所(2025.10.30)
夫婦それぞれの収入(給与所得・自営業所得など)と子どもの人数・年齢区分をもとに、平均的な生活費を推定して養育費の目安を導き出す仕組みです。
例えば、支払う側の年収が600万円、受け取る側の年収が100万円で、子どもが1人(14歳未満)の場合、算定表上の目安は月額6〜8万円程度となります。
算定表は「標準的な生活水準」を基準にしているため、実際の家庭事情によって上下することがあります。
例えば、子どもが私立学校に通っている、医療的ケアが必要など特別な事情がある場合は、調停や審判の場で加減算されることもあります。
収入の定義と注意点
算定表における「年収」とは、源泉徴収票の「支払金額」(各種社会保険料等が控除されていない金額、いわゆる「額面」とか「総支給」と言われる金額)です。
算定表による相場感を理解するための具体例
たとえば、支払う側が年収500万円、受け取る側が年収100万円、子どもが2人(10歳と8歳)の場合、目安は月8〜10万円程度です。
一方、支払う側の年収が300万円程度の場合、同条件でも月4〜6万円程度です。
このように、年収差・子どもの人数によって養育費は大きく変動します。また、私立の学校に行っている場合にも、学費が一定額加算される場合があります。
相場より高い・低い取り決めをする際の注意
当事者間の話し合いで相場より高い金額を設定することは可能ですが、将来的に支払いが困難になった場合のリスクもあります。
反対に、相場より低い金額で合意してしまうと、子どもの教育費や医療費を賄えなくなるおそれがあります。
そのため、P&M法律事務所では、算定表を基礎にしつつ、実際の生活費や進学希望を踏まえ、法律的に可能な範囲でできる限り相当な金額に落ち着けることを目標としています。
養育費を決めるタイミングと方法(協議・調停・審判)
養育費は、離婚の話し合いと同時に決めるのが理想です。
離婚が成立してから請求しようとすると、支払い開始までに時間がかかるうえ、相手の収入状況が変わって不利になることもあります。
したがって、離婚協議書や公正証書、もしくは家庭裁判所での調停手続きの中で取り決めを行うのが一般的です。
養育費を定める主な方法は次の3つです。
(1)協議離婚での取り決め
夫婦の話し合いで離婚が成立する場合、同時に養育費の金額・支払期間・支払方法を合意します。
この際は、公正証書を作成しておくことが非常に重要です。公正証書には「支払いが滞った場合、強制執行に服する」という文言を入れることができ、後に相手が支払わなくなっても差押えが可能になります。
(2)調停離婚での取り決め
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」や「離婚調停」を申し立て、調停委員を介して金額を協議します。
調停で合意が成立すると、「調停調書」が作成され、これは判決と同じ法的効力を持ちます。
(3)審判・裁判での決定
調停でも合意に至らない場合、裁判所が最終的に金額を決定します。
審判や裁判では、収入証明や生活費の明細、養育環境などを証拠として提出し、裁判官が算定表を基に妥当な額を判断します。
養育費を請求する流れと必要書類
養育費を請求するには、まず相手方に支払い義務があることを明確にする書類が必要です。
具体的な流れは次の通りです。
(1)協議または内容証明郵便での請求
まずは書面で養育費の支払いを求めます。
「いつから」「いくら」「どの口座に」支払うのかを明記し、後に証拠として残せるよう内容証明郵便で送付するのが望ましいです。
この段階で合意できれば、公正証書を作成して法的効力を持たせます。
(2)調停申立て
話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てます。
必要書類は以下の通りです。
申立書
戸籍謄本(子どもを含むもの)
収入証明書(源泉徴収票・確定申告書など)
支出に関する資料(家計簿、学校費用の領収書など)
調停委員が双方の収入状況や生活実態を踏まえ、算定表を基に合意案を提示します。
(3)審判・裁判
調停で不成立になった場合は、自動的に審判に移行するか、改めて訴訟を提起します。
弁護士が代理人として主張立証を行い、裁判官が最終的に養育費額を決定します。
養育費の支払い方法と支払期間
(1)支払い方法
養育費は通常、毎月一定額を銀行振込で支払う形で定めます。
現金手渡しは証拠が残りにくいため避けるべきです。
銀行振込であれば、入金記録が支払い証拠となり、後のトラブル防止につながります。
また、年単位や一括払いを希望する場合もありますが、将来的な収入変動リスクを考えると、月払いがもっとも安全です。
(2)支払い期間
原則として、子どもが社会的に自立するまでが支払いの対象です。
具体的には、大学進学を想定して22歳(大学卒業の年度末)までとするケースが増えています。
一方で、高校卒業時(18歳)までと定める合意もあり、個別事情に応じて決められます。
(3)支払い開始時期
養育費の支払いは、原則として離婚成立の翌月から開始されます。
ただし、離婚前の別居期間中に調停が行われた場合、その間の「婚姻費用分担金」との整合性を取る必要があります。
弁護士が関与すれば、二重請求や期間重複を防ぎ、適正な時期から支払いが始まるよう整理してもらえます。
養育費が支払われない場合の対応
養育費は子どもの生活を支える重要な費用ですが、実際には約4割のケースで途中から支払いが滞るという統計もあります。
ここでは、合意された養育費の支払いが止まった際に取るべき対応を紹介します。
(1)任意の請求(催促)
まずは、相手方に電話・メール・書面で支払いを促します。
記録を残すために、内容証明郵便での催促が有効です。
(2)履行勧告・履行命令
家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が相手方に「支払いを勧告」する制度があります。
強制力は弱いものの、裁判所名義の通知が届くことで心理的プレッシャーを与える効果があります。
さらに悪質な場合には「履行命令」を申し立てることも可能で、支払わない理由が正当でないと判断されれば10万円以下の過料が科されることもあります。
(3)強制執行(差押え)
最も確実な手段は、強制執行による給料や預金の差押えです。
調停調書・公正証書・判決などの「債務名義」があれば、弁護士を通じて強制執行手続きを行うことができます。
相手方の勤務先や金融機関を特定する必要がありますが、弁護士であれば職権照会制度などを活用して調査を行うことが可能です。
養育費の増額・減額の手続き
養育費は一度決めたら永久に固定されるわけではありません。
生活環境や収入状況が大きく変わった場合には、家庭裁判所を通じて変更(増額・減額)を求めることが可能です。
(1)増額を求めるケース
次のような場合には、支払い額の引き上げが認められることがあります。
子どもの進学で教育費が増えた(高校・大学への進学など)
子どもの病気や障がいにより医療費が増加した
支払う側の収入が上がった
物価上昇などで実質的な生活費が増えた
特に教育費の上昇は頻繁に問題となる項目です。
公立から私立に進学する場合などは、明確な支出増として認められやすい傾向にあります。
(2)減額を求めるケース
逆に、支払う側が以下のような事情に該当する場合には、減額が認められる可能性があります。
失業や病気で収入が減少した
再婚して新たな扶養家族が増えた
相手が再婚し、生活環境が改善した
ただし、「一時的な減収」「支払いが面倒になった」という理由では認められません。
裁判所はあくまで「継続的な経済事情の変化」があるかを厳格に判断します。
(3)手続きの流れ
増減額を求める場合は、「養育費変更調停」を家庭裁判所に申し立てます。
双方の収入資料や生活費の明細をもとに、調停委員が再度妥当な金額を検討します。
合意に至れば調停成立、不成立なら審判で決定されます。
弁護士が関与すれば、調停申立書の作成や資料提出を代行し、法的根拠を明示した説得的な主張を行ってくれます。
弁護士に依頼するメリットと費用感
養育費の取り決めは個人でも行えますが、実務的には弁護士に依頼した方が確実で結果的に負担が少ないケースが多くあります。
ここでは、主なメリットと費用の目安を紹介します。
(1)法律的根拠に基づいた適正額の算定
算定表はあくまで「平均的な目安」に過ぎず、個別事情を反映させるには専門知識が必要です。
弁護士は最新の判例や生活実態をもとに、適正かつ持続可能な金額設定を行います。
特に高収入者や自営業者の場合、算定表だけでは対応できない特殊事情を主張しやすくなります。
(2)交渉・調停・裁判すべてに対応可能
相手が話し合いに応じない場合でも、弁護士が代理人として調停や訴訟を行います。
直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。
また、調停委員とのやり取りも法律的に整理され、誤解や不利な発言を防げるのも大きな利点です。
(3)支払いが滞った場合の迅速な対応
調停調書や公正証書がある場合、弁護士はすぐに強制執行(差押え)手続きを行うことが可能です。
勤務先や金融機関の特定、照会請求、申立書作成など、専門的な作業を迅速に進められます。
(4)費用の目安
P&M法律事務所では、次のような料金体系となっています。
相談料:初回無料(時間制の場合もあり)
着手金:33万円~(税込み)
調停着手金 44万円~(税込み)
訴訟着手金 55万円~(税込み)
成功報酬(下記は目安であり、事案によって増減します)得られた経済的利益の8%~18%程度
実費:印紙代・郵送費など1〜2万円程度
よくある質問(FAQ)
養育費に関し、よくいただく質問を掲載します。
まとめと弁護士相談のすすめ
養育費は、離婚後の子どもの生活を支える命綱です。
取り決めがあいまいなまま離婚してしまうと、後で支払いが途絶えたり、必要な金額が得られなかったりするリスクが高まります。
そのため、離婚時点で明確な金額・期間・支払方法を定め、書面化することが不可欠です。
また、養育費は一度決めたら終わりではなく、子どもの成長や親の経済状況に応じて見直すことができます。
調停や強制執行などの手続きも含め、専門的なサポートを受けることで、無理なく・確実に権利を守ることができます。
P&M法律事務所では、離婚や養育費の取り決めに関する初回相談を無料で受け付けています。
経験豊富な弁護士が、あなたとお子さまの将来を見据えた最適な解決方法をご提案します。
「相手が支払いに応じない」「金額が妥当かわからない」「調停を申し立てたい」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの大切なお子さまの生活を守るために、私たちが全力でサポートいたします。
ケーススタディ(架空のもの)
養育費の問題は、法律上の理屈だけでなく「現実の生活」と密接に関わっています。事例を用いて、どのように対応するのか、具体的な対応方法をご紹介します(実際にあった事例ではありませんので、ご注意ください)。
事例①:支払いが途絶えたケース
状況
離婚時に月5万円の養育費を公正証書で取り決めていたが、元夫が転職を理由に半年間支払いを停止。母親が再三連絡しても応じず、生活が苦しくなった。
想定される弁護士の対応
公正証書があるので裁判を介さずに強制執行。
勤務先が知れていたので、給与の一部を差押える形で未払い分を回収。
ポイント
支払いが滞った場合、感情的に訴えても改善しないことが多いです。
「強制執行に必要な債務名義(公正証書・調停調書)」を準備しておくことが最大の防御策となります。
事例②:収入減による減額請求
状況
父親側(支払義務者)が病気で長期休職し、収入が半減。
しかし、元妻からの養育費(月7万円)の減額交渉に応じてもらえず、支払いが苦しい状況に。
弁護士の対応
家庭裁判所に「養育費減額調停」を申立て、収入証明・診断書などを提出。
調停委員を通じて元妻にも現実的な説明を行い、月4万円に減額。
ポイント
調停委員は「感情ではなく事実」で判断します。
医師の診断書、給与明細、源泉徴収票など客観的な証拠の準備が重要です。
事例③:子どもの進学による増額請求
状況
母親側(監護者)が高校生の子どもの大学進学を控え、学費負担が急増。
現行の養育費(月3万円)ではまかないきれないため、増額を希望。
弁護士の対応
大学入学金・授業料・家賃の見積書などを提出し、将来の支出計画を具体的に提示。
調停で月6万円への増額が合意され、進学資金を確保。
ポイント
教育費の増加は「事情変更」にあたります。
この場合、感情論ではなく「数字で説得する」ことが大切です。
弁護士が資料を体系的に整理することで、調停委員や裁判官に納得してもらいやすくなります。
事例④:合意書を作らずに離婚してしまったケース
状況
話し合いで離婚し、口頭で「毎月4万円払う」と約束したものの、1年後には支払いが途絶。
証拠がないため強制執行もできず、再請求に苦労。
弁護士の対応
まず「養育費請求調停」を申し立て、正式な合意書(調停調書)を作成。以降の養育費を回収。
ポイント
口約束では法的拘束力がありません。公正証書または調停調書として書面化することが、トラブル防止の基本です。
弁護士が重視する「3つの視点」
① 法的安定性 → 調停・公正証書など「執行できる形」で取り決める。
② 現実的持続性 → 支払う側・受け取る側の双方が無理なく継続できる額を設定。
③ 将来見通し → 子どもの成長(進学・医療)を見据えて長期設計を行う。
この3点を意識することで、単なる金額交渉ではなく「子どもの将来を守る仕組み」としての養育費を構築できます。
弁護士からのメッセージ
P&M法律事務所では、「相手が払わない」「調停を申し立てたい」「金額の妥当性を確認したい」といったご相談を数多く受けています。
私たちは単に法的手続きを行うだけでなく、依頼者とお子さまの生活設計を一緒に考えることを重視しています。
弁護士に相談することで、冷静に、そして確実に問題を解決できます。
養育費に関する悩みを一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
関連記事
-

離婚後の住宅ローンはどうなる?トラブルを回避するための方法をご紹介
-


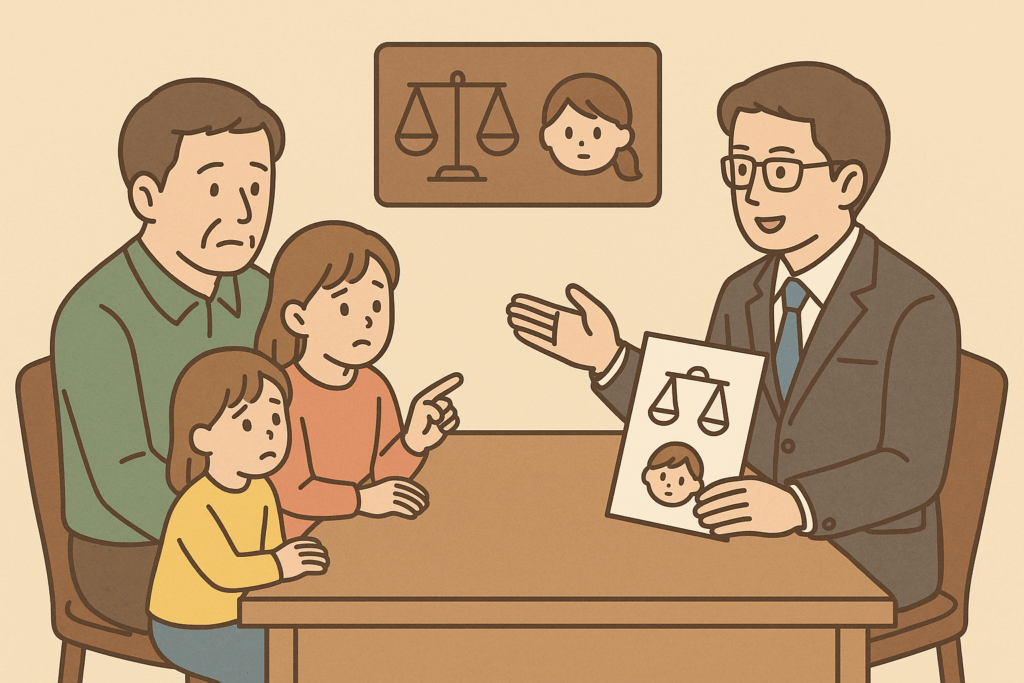
離婚時の親権はどうなる?親権者の決め方や注意点を離婚に強い弁護士が解説
-


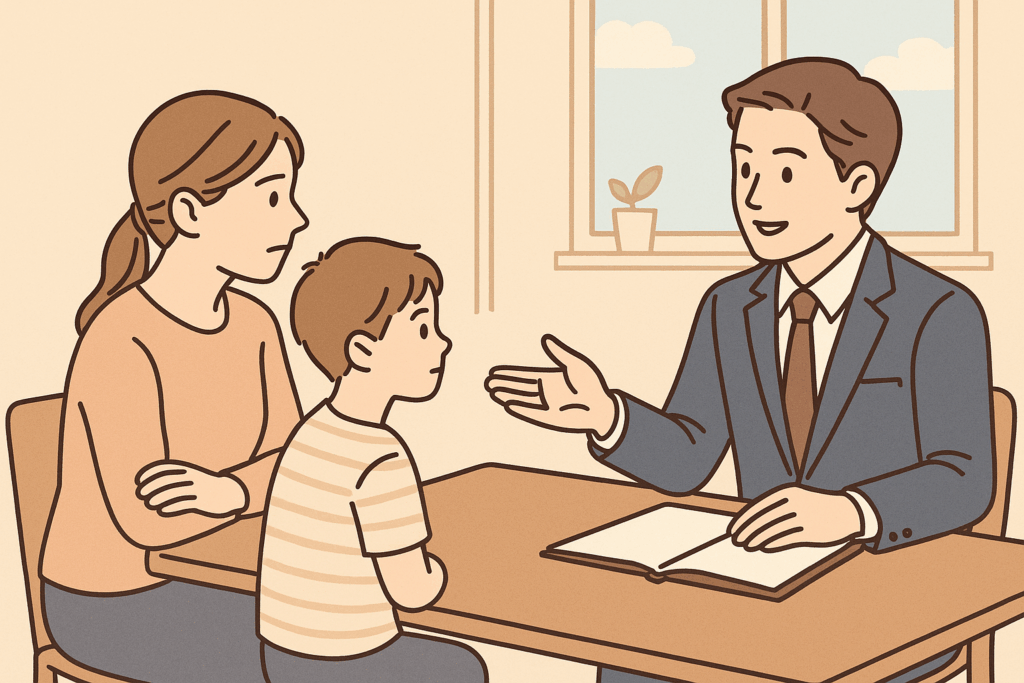
離婚時に定める養育費とは?相場から請求方法の流れまで分かりやすく解説
-


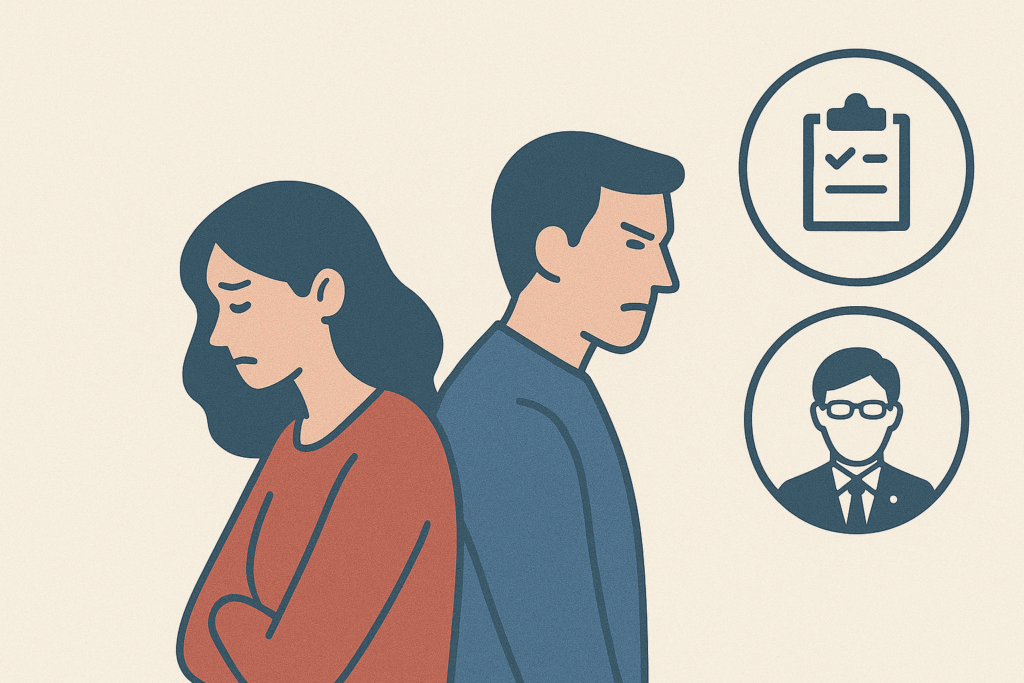
離婚調停とは?申立ての流れや費用・気を付けるポイントまで弁護士が解説
-



婚姻費用を請求されたら?支払い義務と決定後の減額交渉のポイント
-



不貞行為はどこから?離婚事由、慰謝料が発生するケースも紹介!
-


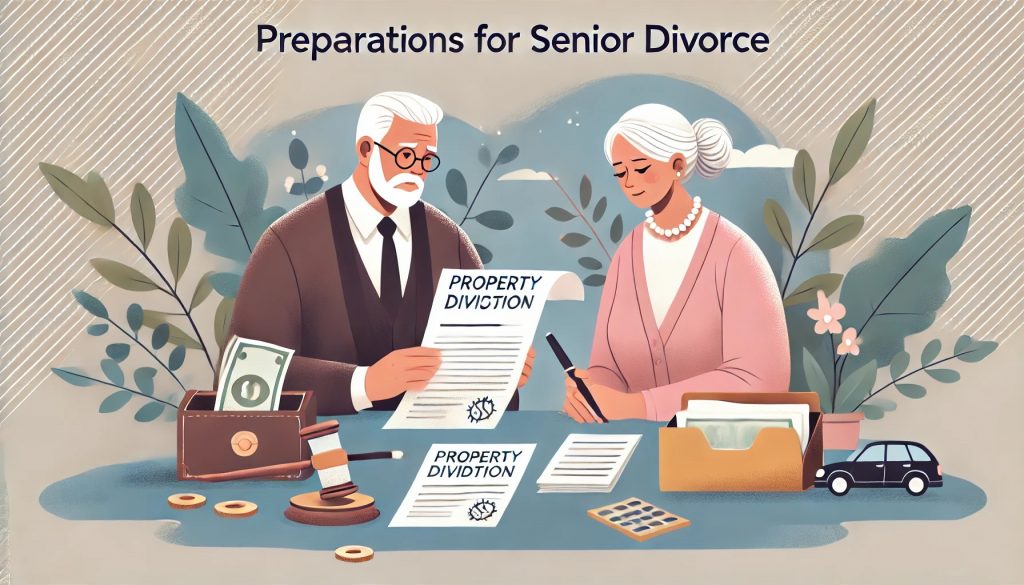
熟年離婚を思い立ったら読む記事
-



増え続ける熟年離婚、考えておくべきポイント・注意点
-



離婚の慰謝料の相場とは?弁護士に相談したほうがいい場合も解説!
-


に向けて別居前にすべき7つのこと-1024x576.jpg)
高所得者との離婚(財産分与)に向けて別居前にすべき7つのこと
-



離婚に際して財産分与をする場合~隠し財産の探し方~
-



離婚後の相続について解説!子供の相続や困った場合の相談先を紹介