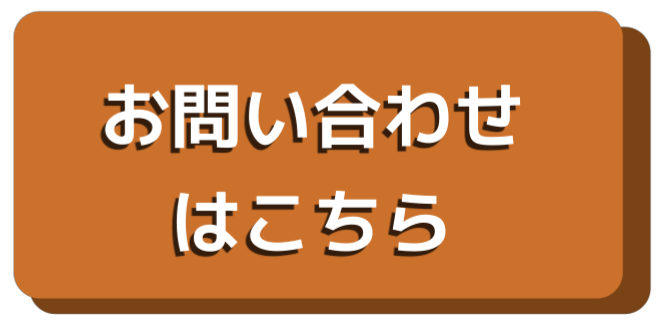離婚調停とは?申立ての流れや費用・気を付けるポイントまで弁護士が解説

離婚を考えているけれど、夫婦間の話し合いが平行線をたどっている―そんなときに利用されるのが「離婚調停」です。離婚調停は、裁判よりも柔軟に話し合いができる公的な手続きであり、家庭裁判所で行われます。
この記事では、離婚調停の流れ・費用・注意点を、弁護士の立場からわかりやすく解説します。さらに、弁護士に依頼するメリットや、後悔しないための準備のポイントについても詳しく紹介します。
離婚調停とは?裁判との違いと特徴
離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員(男女各1名)を介して夫婦が話し合いを行う制度です。法律上は「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれ、家庭裁判所調停の中でも件数が最も多い手続きのひとつです。
調停は、離婚を成立させることを目的とする場合もあれば、「別居中に話し合いの場を設けたい」「養育費や面会交流を取り決めたい」など、部分的な問題解決のために利用されることもあります。
裁判と異なるのは、あくまで「話し合いによる合意」を目指す点です。裁判では判決により白黒をつけますが、調停では双方の主張をすり合わせ、円満な解決を目指します。そのため、感情的な衝突を避けつつ、柔軟な合意形成が可能となります。
離婚調停の申し込みから成立までの流れ
① 調停申立て
離婚調停は、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に対して申立てを行うことで始まります。申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立書には、離婚を求める理由や希望する条件(財産分与・養育費・親権・慰謝料など)を具体的に記載します。
② 申立て後の手続き
申立てが受理されると、約2〜4週間後に「調停期日呼出状」が裁判所から送付されます。初回期日は通常1か月前後で指定され、平日の日中に設定されることが多いです。
③ 調停期日の進行
期日では、調停委員が双方から事情を聞き、合意点と対立点を整理します。多くの場合、夫婦が直接顔を合わせることはなく、別々の部屋で個別に話を聞く「交互面談方式」がとられます。
調停委員は中立の立場から助言を行い、妥協案を提示するなどして合意を目指します。
④ 合意成立・不成立
話し合いの結果、離婚条件について合意が成立すれば「調停成立」となり、裁判所が作成する調停調書には判決と同等の法的効力があります。
一方、話し合いがまとまらない場合は「調停不成立」となり、離婚裁判へと進むこともあります。
調停の所要期間
離婚調停は平均して3〜6か月程度で終了します。
ただし、双方の主張が平行線をたどる場合や、財産分与・親権をめぐって争いがある場合は1年以上かかることもあります。
実際の調停のリアルな進行
実際の離婚調停は、1回あたりおよそ1〜2時間で、月に1回程度のペースで開かれます。
1回の話し合いで結論が出ることはまれで、平均すると3〜5回、複雑な事案では10回以上行われることもあります。
期間にすると、おおむね3か月〜半年ほど。親権や高額な財産分与が絡む場合は1年以上に及ぶケースもあります。
たとえば、配偶者の浪費や不倫が原因であっても、相手方が否定する場合には、証拠や経済状況の資料を見ながら慎重に判断が進められます。
また、調停委員は単に意見を伝えるだけでなく、時に当事者の心理面にも配慮します。
「あなたの希望は分かりますが、裁判になった場合にはこう判断されることが多いですよ」
といったように、裁判の見通しを踏まえたアドバイスを与えることも多く、調停の中で自然と合意が形成されていくこともあります。
離婚調停にかかる費用と必要書類
離婚調停の費用は、裁判と比べて低額です。
申立て時に必要な費用は次のとおりです。
収入印紙:1,200円
郵便切手:1,000〜2,000円程度(裁判所によって異なる)
その他、証拠書類のコピー代など実費が発生する程度です。
必要書類の例
申立書(裁判所の書式)
夫婦の戸籍謄本
証拠資料(財産資料、収入証明、子の生活状況など)
家庭裁判所の窓口やウェブサイトからダウンロードでき、個人でも申立ては可能です。
しかし、内容や主張の書き方を誤ると、思うような結果が得られない場合もあります。そのため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
ただし、弁護士に依頼する場合は別途費用が発生します。
一般的には以下が相場です。
着手金:20〜40万円前後
報酬金:得られる財産がある場合にはその8%~18%くらいのことが多い
実費:1万円程度
案件の難易度(財産額、親権争いの有無など)によって増減します。
弁護士に依頼するメリット
有利な条件での合意が期待できる
調停では、財産分与・慰謝料・養育費などの金額をめぐって意見が対立することが多くあります。弁護士は法律と裁判例に基づいて主張を整理し、依頼者に有利な条件を引き出すための交渉を行います。
書類作成・証拠収集を任せられる
調停では、事実を裏付ける資料の提出が重要です。預金通帳や不動産資料、給与明細などをどのように整理して提出するかで、結果が大きく変わることもあります。弁護士が関与すれば、必要な証拠を的確に準備でき、主張に説得力が生まれます。
裁判所とのやり取りを任せられる
申立てや期日調整、提出書類の確認など、裁判所との手続きは煩雑です。弁護士が代理人として対応することで、依頼者は手続き的な負担を大幅に軽減できます。
精神的なストレスを軽減できる
離婚調停では、相手方と意見がぶつかる場面も少なくありません。弁護士が代理人として立ち会うことで、依頼者が直接相手と向き合う必要がなくなり、心理的な負担を減らすことができます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 離婚調停はどのくらいの期間で終わりますか?
平均的には3〜6か月程度ですが、話し合いがスムーズに進めば2回程度の期日で成立することもあります。
逆に、財産分与や親権争いがある場合は1年以上かかることもあります。
たとえば、住宅ローンのある持ち家をどう扱うか、または不動産の評価額をどう算出するかなどの論点があると、時間がかかる傾向があります。
Q2. 調停には毎回出席しなければいけませんか?
原則として本人出席が求められますが、弁護士を代理人に立てれば、弁護士のみの出席が認められることもあります。
特に2回目以降は、本人が仕事を休みにくい場合や精神的に負担が大きい場合、弁護士が代わりに出席して経過報告を行うことが一般的です。
Q3. 相手が調停に来なかった場合はどうなりますか?
裁判所は何度かほど呼出状を送りますが、それでも出席しない場合は「調停不成立」として終了します。
ただし、相手が無視したままでいる場合には、その経過自体が「話し合いができない証拠」として裁判で有利に働くこともあります。
Q4. 調停委員はどんな人が担当するのですか?
家庭裁判所が任命する男女ペアの有識者で、弁護士、心理カウンセラー、元公務員などが多いです。
中立的立場で話を聞き、時に現実的なアドバイスをくれる存在です。
ただし、調停委員によって経験値や対応の柔らかさに差があるため、理不尽な対応を受けた場合は弁護士を通じて意見を伝えることも可能です。
Q5. 話した内容は記録に残りますか?
調停委員が要点を記録しますが、すべての発言が調書に残るわけではありません。
調停成立時には、合意内容のみが「調停調書」としてまとめられ、これが法的効力を持ちます。
一方で、感情的な発言や非公開情報は記録に残さない配慮もあります。
Q6. 調停の場で相手を責めすぎると不利になりますか?
はい。調停はあくまで「冷静な話し合いの場」です。
感情的な発言を繰り返すと、調停委員から「協調性がない」と受け取られ、不利に働くこともあります。
事実や証拠に基づき、淡々と説明することが大切です。弁護士が同席していれば、言葉の選び方をフォローしてくれるため安心です。
Q7. 財産分与や慰謝料の金額はどのように決まりますか?
基本的には共有財産の半分ずつが原則です。
慰謝料は不貞・暴力・浪費などの事情により個別に判断され、一般的には50〜300万円程度が目安です。
弁護士が関与すると、財産資料を基に正確な算定を行い、「相場より低い提示」に即座に異議を出せるため、有利に交渉が進みます。
Q8. 子どもの親権はどのように判断されますか?
親権争いでは、子どもの福祉(安定した生活・教育環境・養育能力)が最も重視されます。
「母親だから」「収入が多いから」といった単純な基準ではなく、日常的にどちらが子どもの世話をしてきたかが焦点です。
弁護士は家庭裁判所の実務を踏まえて、写真・日記・通園記録などを証拠としてまとめるサポートを行います。
Q9. 調停が不成立になったらどうすればいいですか?
不成立の場合は、自動的に離婚裁判に移行できます。
ただし、裁判では調停の記録(提出書類・発言要旨など)が参照されることがあるため、調停段階から弁護士が戦略的に発言内容を管理しておくことが重要です。
調停での準備がそのまま裁判の土台になると考えておきましょう。
離婚調停で注意すべきポイント
感情的にならず、事実と希望を整理して伝える
調停は「感情のぶつけ合いの場」ではなく、「冷静な話し合いの場」です。
怒りや不満をそのまま伝えてしまうと、調停委員の理解を得にくくなります。主張したいことは事前にメモなどで整理し、落ち着いて伝えるようにしましょう。
証拠・資料を客観的に揃える
「相手が浮気した」「生活費を入れてくれなかった」といった主張には、客観的な証拠が必要です。LINEのやり取り、通帳、領収書など、日常の記録が証拠になります。 弁護士に相談すれば、どの資料が有効かを具体的にアドバイスしてもらえます。
子どもの利益を最優先に考える
親権や養育費をめぐる話し合いでは、子どもの福祉が最も重視されます。
「どちらがより安定した生活環境を提供できるか」が判断基準となるため、日常の世話の実態や教育環境を丁寧に説明できるよう準備しておきましょう。
不成立の場合の次のステップも想定しておく
調停が不成立となった場合、自動的に裁判に移行することもあります。
このとき、調停で提出した資料や発言内容は裁判で参照される可能性があるため、最初から慎重な姿勢で臨むことが大切です。
弁護士への相談は「申立前」が理想
離婚調停の成功は、事前準備の質に左右されます。申立て前に弁護士へ相談しておけば、
どの主張を優先すべきか
提出すべき証拠は何か
どの条件を譲れないか
といった戦略を立てることができ、調停を有利に進められます。
また、相手方に弁護士がついている場合、知識や交渉力に差が出るため、こちらも専門家を立てて対応することが望ましいです。
弁護士に依頼するメリット
法的な主張を的確に伝えられる
調停では、感情的な発言が先行してしまい、肝心の主張が調停委員に正しく伝わらないことがあります。
たとえば、「相手が生活費を入れなかった」という主張を裏付けるには、銀行通帳や家計簿の提示が必要です。
弁護士がつけば、どの証拠をどのように整理すれば説得力があるかを具体的に指導してもらえるため、調停委員や裁判官に効果的に訴えることができます。
書類作成や証拠提出を代行してもらえる
調停では申立書・陳述書・財産目録など多数の書類を作成します。
たとえば「住宅ローンがある持ち家をどう分けるか」といった複雑な問題では、残債や名義の確認、評価証明書の提出が必要です。
弁護士に依頼すれば、これらを法的観点から整理し、必要書類を整えて提出してくれます。
相手とのやり取りを避けられる
感情的な対立がある場合、相手方と直接話すことは大きなストレスになります。
弁護士を代理人に立てると、相手方とのやり取りはすべて弁護士を通して行われ、心理的な負担が大幅に減ります。
DVやモラハラ事案では特に、弁護士が前面に出ることで安全に調停を進められるという利点があります。
不成立時にもスムーズに対応できる
もし調停が不成立となった場合、そのまま離婚裁判へ進むことが多いです。
弁護士がすでに関与していれば、調停で整理した資料や主張を引き継ぎ、裁判への移行がスムーズになります。
最初から弁護士が入っていれば、調停が不成立になっても無駄な手戻りがなく、スピーディーな対応が可能です。
P&M法律事務所では、離婚調停をはじめとする家族法案件を数多く扱っており、法的なサポートと心理的なケアの両面から依頼者を支えています。初回相談では、調停申立ての可否や今後の方針を丁寧にアドバイスしています。
まとめ
離婚調停は専門家のサポートで納得の解決を
離婚調停は、裁判よりも柔軟で穏やかな解決を目指せる制度ですが、法的知識や準備が不十分だと不利な条件で合意してしまうこともあります。
特に、財産分与・養育費・親権など人生に大きく関わる問題では、専門家の助言が欠かせません。
弁護士に依頼することで、主張の整理、証拠収集、交渉、書類提出までを一貫してサポートしてもらえます。
一人で悩む前に、ぜひ一度専門家へご相談ください。
P&M法律事務所では、離婚調停に関する初回相談を受け付けています。
「どのように進めたらいいかわからない」「相手と話し合いができない」といったお悩みにも、経験豊富な弁護士が丁寧に対応いたします。
離婚問題で後悔しないために、まずは専門家への一歩を踏み出してみてください。
-

弁護士は見た!モラハラをする人の特徴5選 典型例・慰謝料になるケースまで徹底解説
-



離婚後の住宅ローンはどうなる?トラブルを回避するための方法をご紹介
-


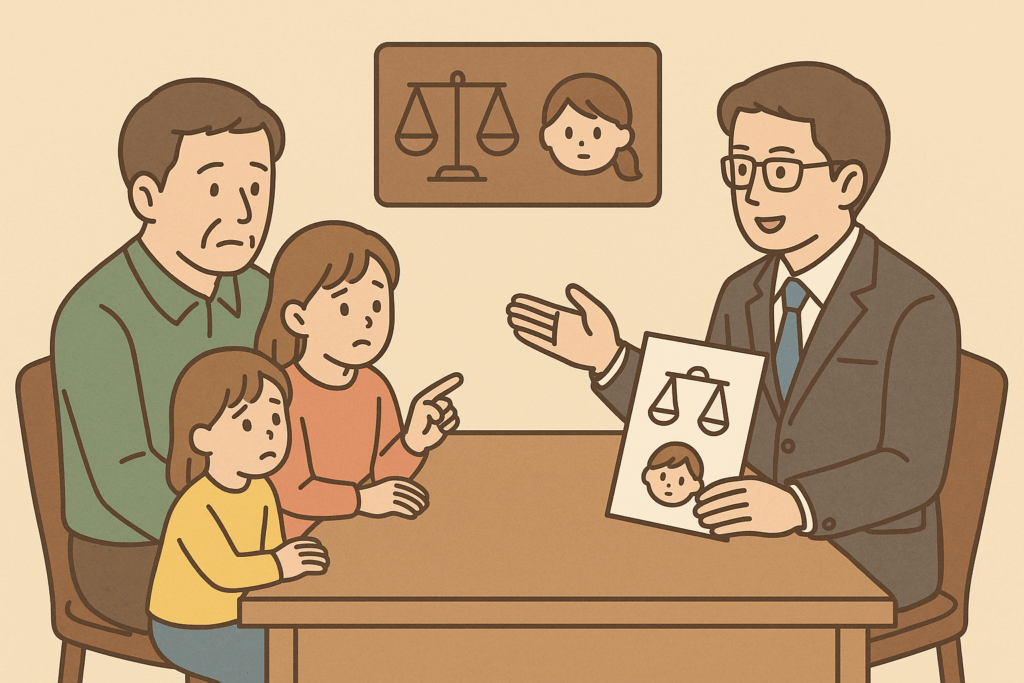
離婚時の親権はどうなる?親権者の決め方や注意点を離婚に強い弁護士が解説
-


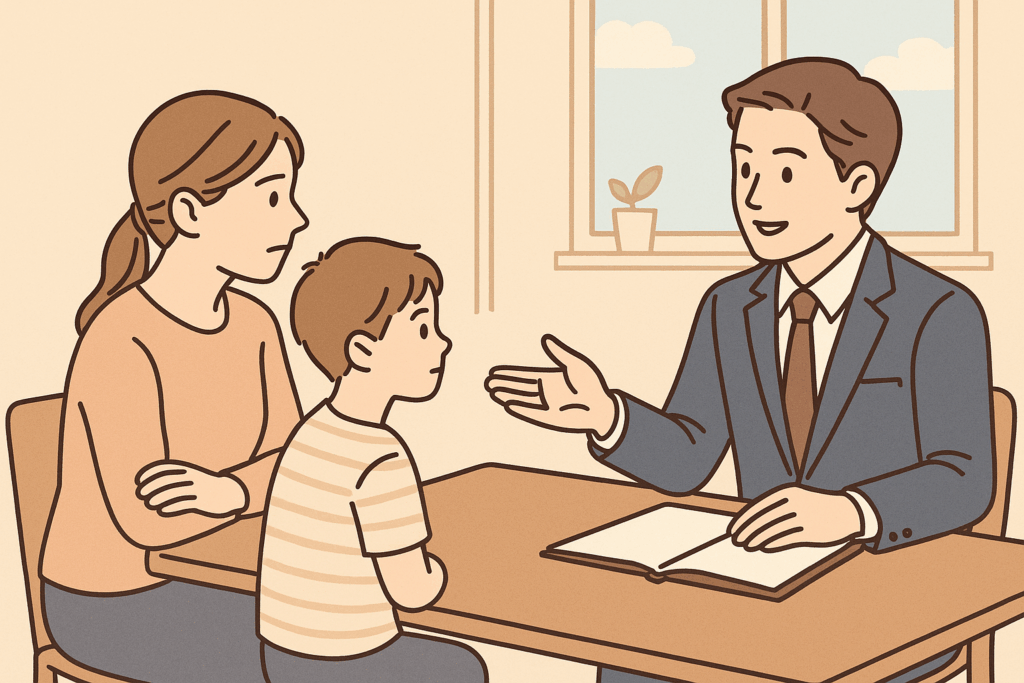
離婚時に定める養育費とは?相場から請求方法の流れまで分かりやすく解説
-


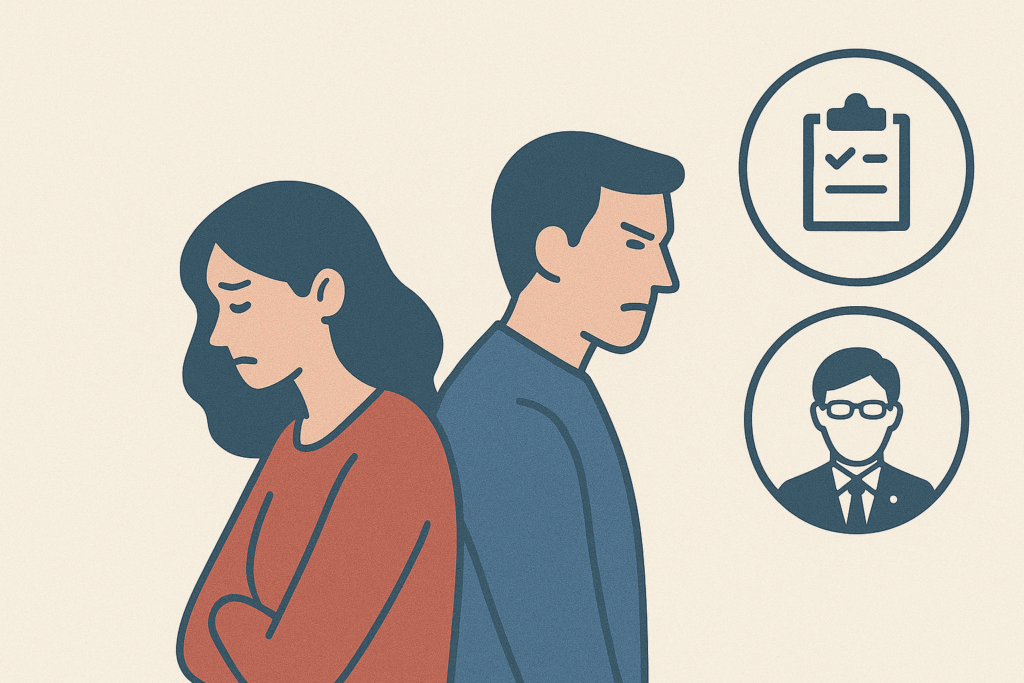
離婚調停とは?申立ての流れや費用・気を付けるポイントまで弁護士が解説
-



婚姻費用を請求されたら?支払い義務と決定後の減額交渉のポイント
-



不貞行為はどこから?離婚事由、慰謝料が発生するケースも紹介!
-


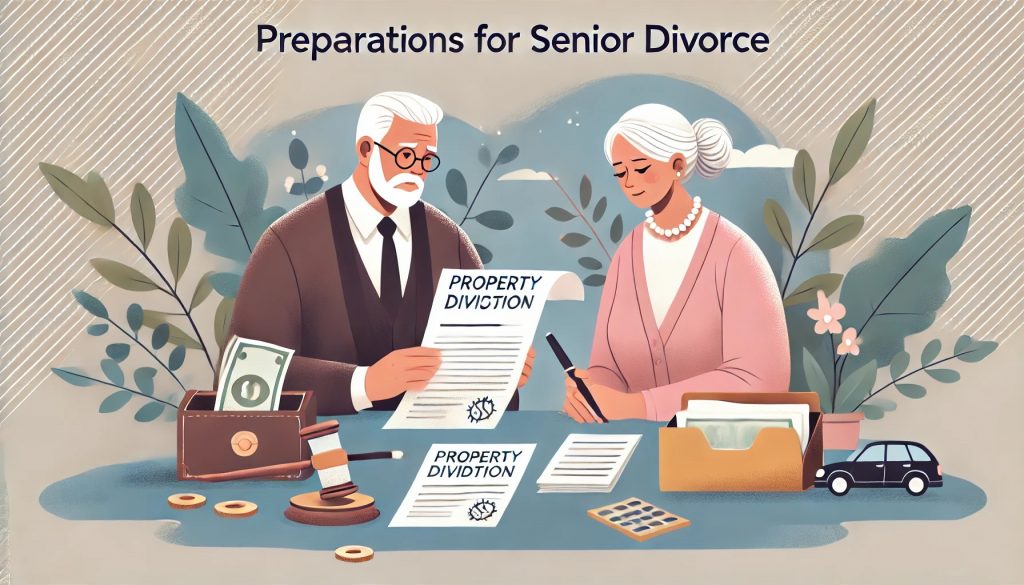
熟年離婚を思い立ったら読む記事
-



増え続ける熟年離婚、考えておくべきポイント・注意点
-



離婚の慰謝料の相場とは?弁護士に相談したほうがいい場合も解説!
-


に向けて別居前にすべき7つのこと-1024x576.jpg)
高所得者との離婚(財産分与)に向けて別居前にすべき7つのこと
-



離婚に際して財産分与をする場合~隠し財産の探し方~


P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」