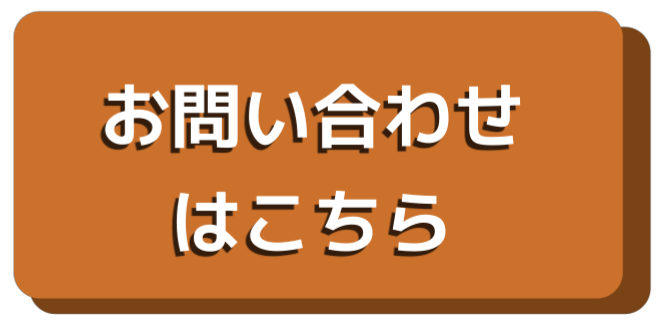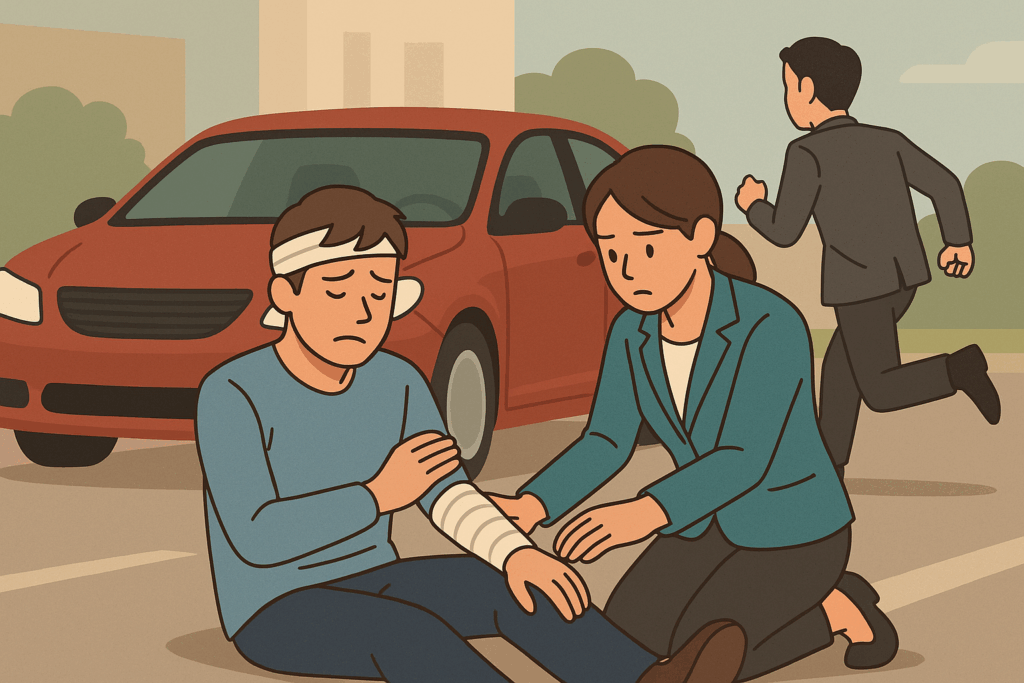休業損害の計算方法とは? 交通事故被害者が適切な賠償を受け取るためのポイント

交通事故の被害に遭い、治療のために仕事を休まなければならなくなった場合、収入が減少してしまうことがあります。このような状況では、「休業損害」として、失われた収入の補填を加害者側に請求できる可能性があります。しかし、どのように計算すればよいのか、どの基準が適用されるのか、どのような証明が必要なのかが分からず、不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、休業損害の基礎知識から具体的な計算方法、職業ごとの違い、請求時の注意点まで詳しく解説します。適切な補償を受け取るために重要なポイントを押さえ、保険会社との交渉や弁護士への相談をスムーズに進めるための参考にしてください。
この記事でわかること
・休業損害とは何かわかる
・休業損害の計算方法がわかる
・休業損害を請求する際の注意点がわかる
休業損害とは?
交通事故によりケガを負った場合、治療のために仕事を休まざるを得ないことがあります。その結果、給与が減少したり、事業の収益が低下したりすることがあり、このような経済的損害を補填するために「休業損害」を請求することが可能です。
休業損害の具体的な内容
休業損害とは、事故によって労働ができず、本来得られるはずだった収入が減少した場合に補填される損害です。給与所得者だけでなく、個人事業主や専業主婦(主夫)も請求できるケースがあります。
慰謝料とは性質が異なり、休業損害は実際の経済的損失を補填するもので、慰謝料は事故による精神的苦痛に対する補償です。そのため、両方の請求が可能です。
また、休業補償とも異なります。 「休業補償」は、労災保険による補償制度であり、勤務中や通勤中に事故が発生した場合に適用されるものです。一方、「休業損害」は、加害者に対して請求する賠償の一部であり、交通事故による損害を対象としています。
休業損害の計算方法
休業損害の金額は、以下の計算式で求めることができます。
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数\text{休業損害} = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
計算基準は3種類ある
休業損害を計算する際には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準:1日6,100円を基準として計算。ただし、証明できる収入がある場合は1日19,000円を上限に実収入ベースで計算可能。
- 任意保険基準:保険会社独自の基準で計算されるため、具体的な金額はケースによるが、自賠責基準よりは高額になる傾向。
- 弁護士基準(裁判所基準):裁判での判例に基づいた基準。実収入をベースに計算されるため、最も高額な賠償が認められることが多い。
休業日数はどのような日か
休業損害の対象となる休業日数は、次のような日を含みます。
- 医師の指示により安静が必要だった日
- 治療やリハビリのために通院した日
- ケガの影響で出勤や作業が困難だった日
ただし、症状固定後(医学的にこれ以上回復しないと判断された時点)の休業は、休業損害の対象とはなりません。
被害者の職業別計算方法
給与所得者(会社員・公務員)
計算式:休業損害=(事故前3か月の給与合計額÷90日)×休業日数
給与のほか、残業代・各種手当・賞与(ボーナス)が減少した場合も賠償の対象となります。
自営業・個人事業主
計算式:休業損害=(前年の確定申告所得÷365日)×休業日数
ただし、固定費(家賃・従業員給与など)が発生している場合、営業継続のために支出があったことを証明すれば、損害として認められるケースもあります。
専業主婦(主夫)
家事労働も経済的価値があると認められており、専業主婦(夫)でも休業損害を請求できます。
計算式:休業損害=(女性の平均賃金÷365日)×休業日数
家事の負担割合や、家族構成によっても認定額が変わることがあるため、具体的なケースごとに検討が必要です。
パート・アルバイト
基本的には給与所得者と同じ計算方法ですが、シフト制で働いている場合は、事故がなければ勤務していた日を証明する必要があります。
学生
学生でアルバイトをしている場合、アルバイト収入を基に休業損害を計算できます。また、事故によって就職が遅れた場合は、逸失利益として請求することも可能です。
休業損害請求をする上で気を付けること
収入証明を準備する
給与明細や確定申告書など、収入を証明できる資料を用意することが重要です。
休業損害証明書の提出
給与所得者の場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、休業日数や支給額を明確にしましょう。
他の補償との重複請求に注意
労災保険や健康保険からの給付がある場合、二重請求は認められませんので、どの補償を優先して請求すべきか慎重に判断する必要があります。
適正な賠償を受けるために
適正な賠償を受けるためには、弁護士に依頼することが最も近道であるといえます。下記では、メリットとデメリットを述べます。
弁護士が介入するメリット
弁護士が介入すると次のようなメリットがあります。
- 適切な基準(弁護士基準)での計算を行い、適正な賠償額を獲得できる
- 保険会社との交渉を弁護士に任せることで、精神的な負担を軽減できる
- 休業損害以外の慰謝料や逸失利益についても適正な賠償を求められる
弁護士が介入するデメリット
弁護士に依頼することで生じるデメリットとしては、費用面があります。
弁護士に依頼すると、弁護士費用として少なくない費用が必要となります。
しかしながら、費用面については、交通事故の場合、ご加入の弁護士特約の利用が可能な場合があります。詳しくは、下記の記事をご参照ください。
弁護士特約を使用できる場合は、弁護士に依頼することで最も適切な補償を得られるといえます。

まとめ
休業損害の請求は、正しい計算方法を理解し、適切な証拠を用意することが重要です。特に保険会社の提示額が低い場合は、弁護士を通じて増額交渉を行うことをおすすめします。
保険会社の対応について不満がある場合は下記の記事も参考にしてみてください。

P&M法律事務所では、交通事故の休業損害請求に関する無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」
関連記事
-

ひき逃げで被害者・加害者になったらどうする?弁護士に相談するメリットを解説
-


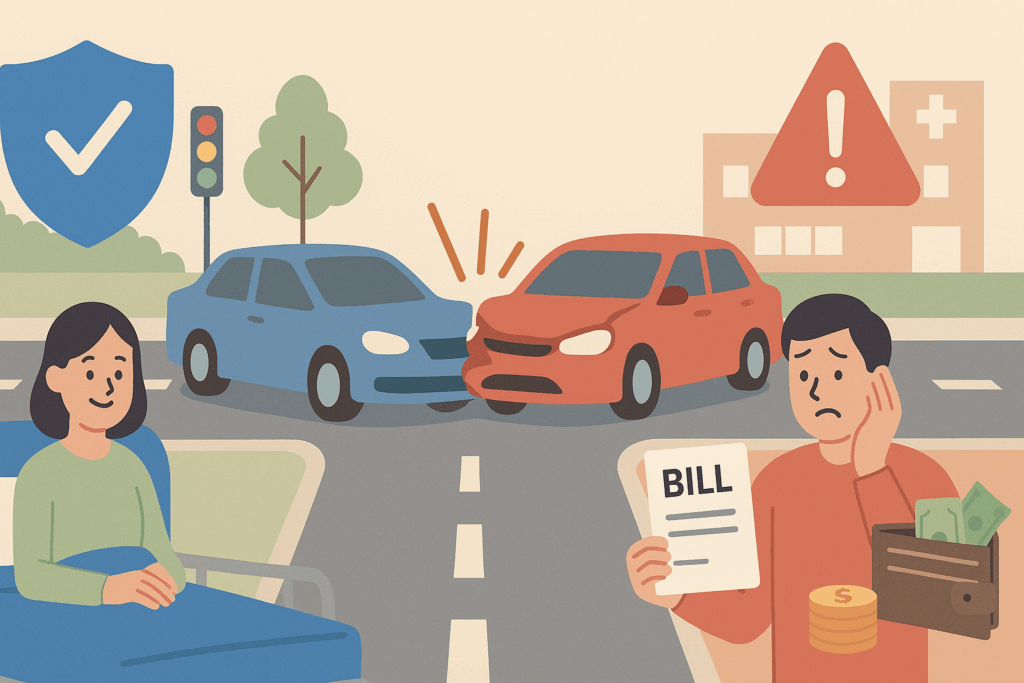
交通事故で保険会社が一括対応してくれる場合とそうでない場合とは?被害者請求の仕組みも解説
-



休業損害の計算方法とは? 交通事故被害者が適切な賠償を受け取るためのポイント
-



交通事故後の保険会社対応に不満を感じたときの対処法
-



交通事故の慰謝料はいつのタイミングで支払われるのか?
-


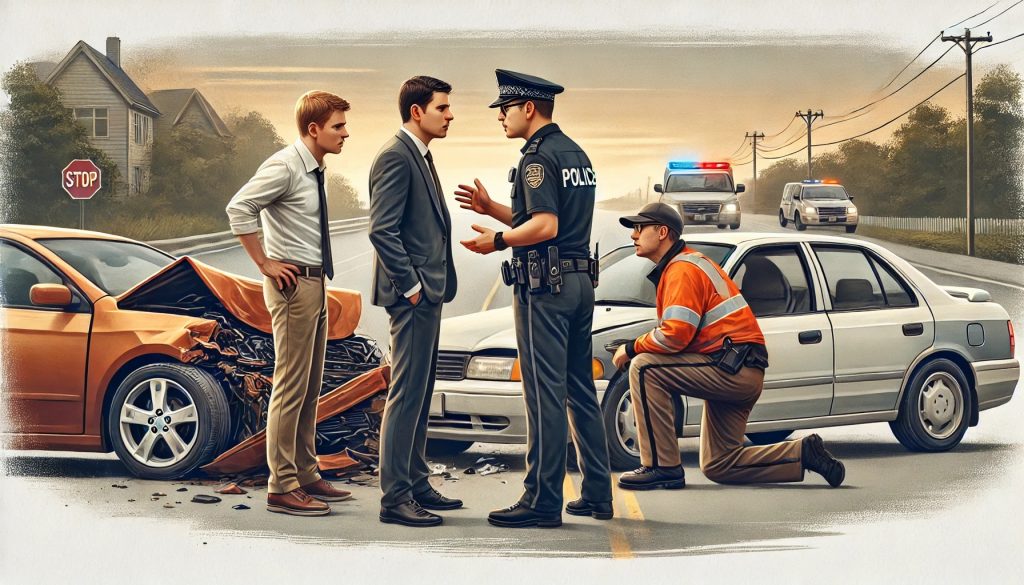
交通事故の加害者から「人身事故で届け出ないで」と言われたら
-



交通事故の過失割合で話がつかない場合~相手がごねる場合の対処~
-



後遺障害4級とは?慰謝料等について詳しく解説
-


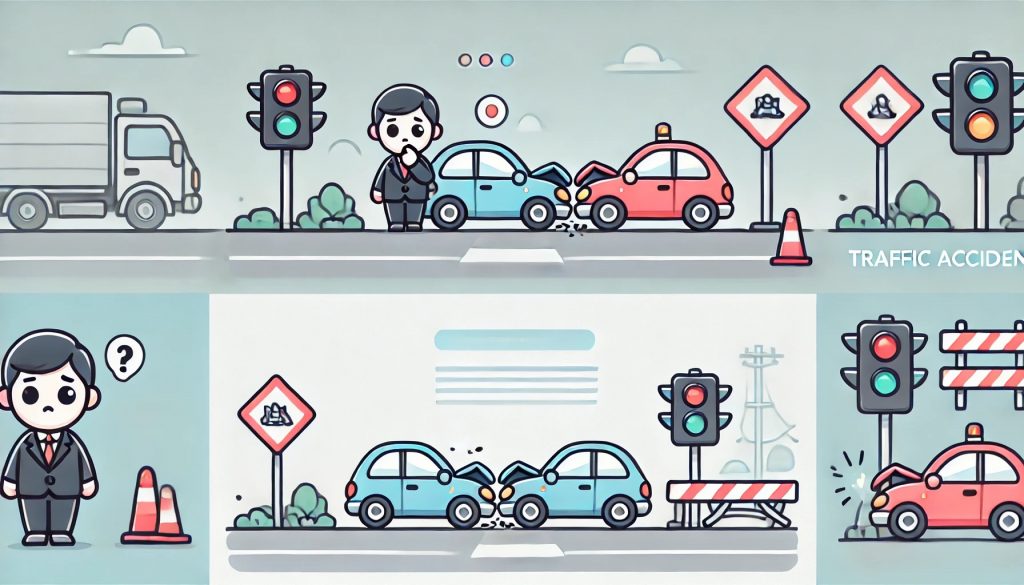
交通事故を人身事故扱いにしないことのデメリット
-



交通事故での後遺障害等級14級とは?内容から認定要素まで
-



休業損害証明書とは? ~作成方法から提出まで~
-



交通事故の弁護士費用特約とは?家族の弁護士特約は使えるか