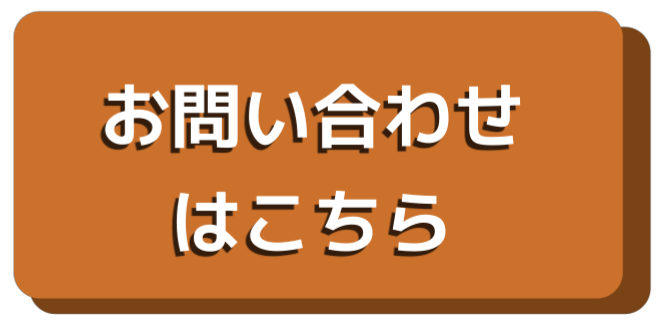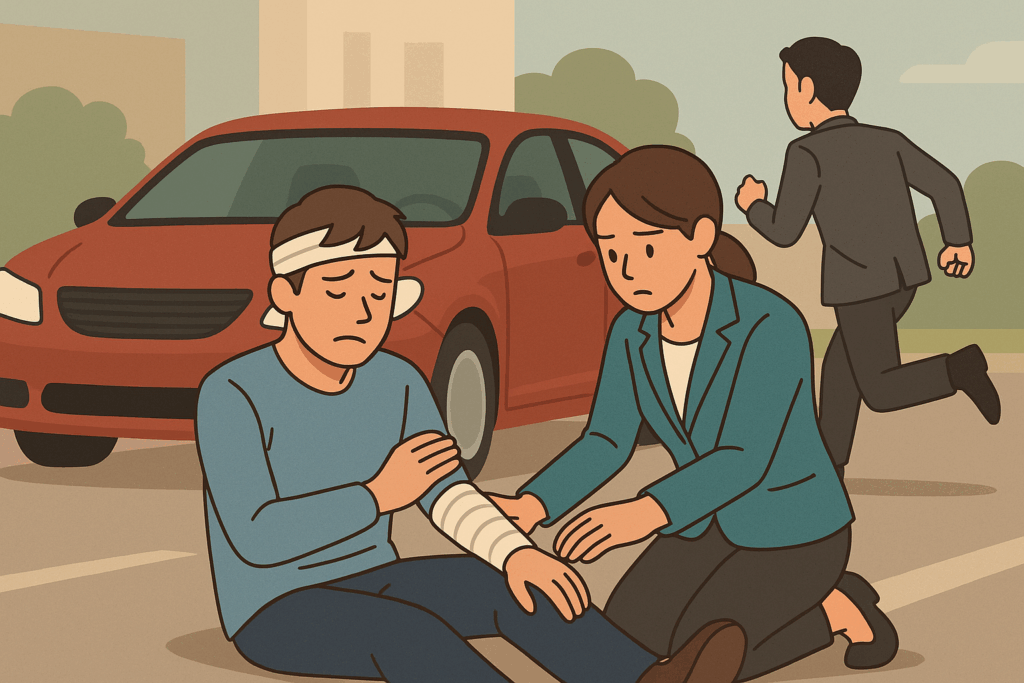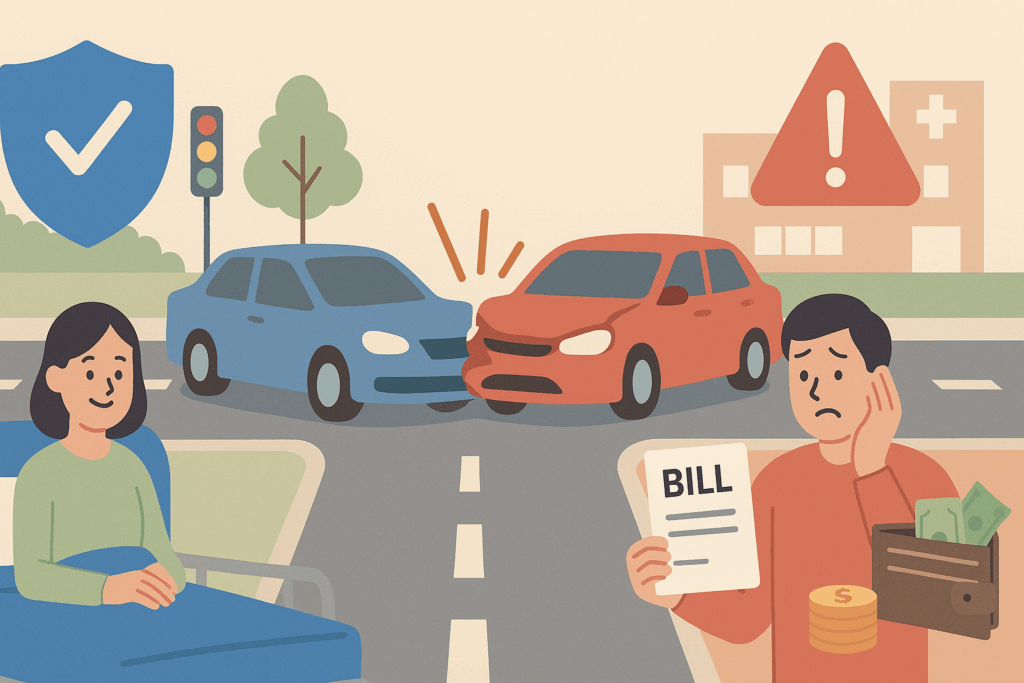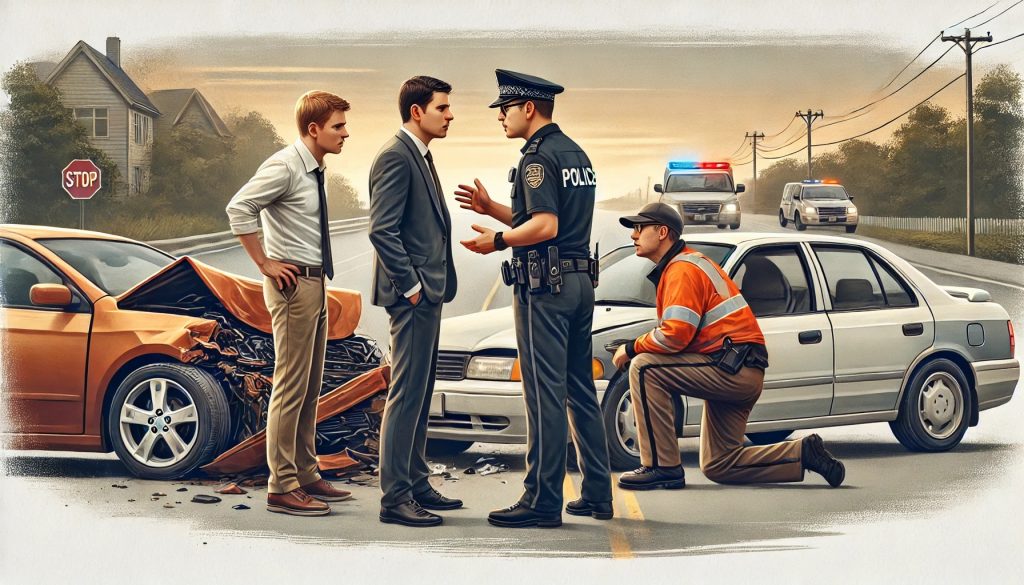ひき逃げで被害者・加害者になったらどうする?弁護士に相談するメリットを解説

ひき逃げは、交通事故の中でも特に重大な犯罪として扱われます。
被害者に怪我を負わせたにもかかわらず、その場から逃走する行為は厳しく処罰されるため、加害者にとっても被害者にとっても、法的な対応を理解しておくことが重要です。
本記事では、ひき逃げの定義や適用される法律、被害者の目線から、刑事・民事上の責任、被害者の目線から対応方法などについて詳しく解説します。
ひき逃げとは?
ひき逃げ(当て逃げとの違い)
ひき逃げとは、交通事故を起こした際に、負傷者の救護や警察への報告をせず、その場から立ち去る行為を指します。ひき逃げと類似する行為として「当て逃げ」がありますが、当て逃げは物損事故(車両や建物への損害)に関するものであり、負傷者が発生していない点が異なります。
ひき逃げ:人身事故で、負傷者を救護せずに逃走
当て逃げ:物損事故で、連絡や報告をせずに逃走
と整理できます。
下記ではひき逃げについて解説していきます。
適用される法律
ひき逃げは、主に以下の法律によって処罰されます。
道路交通法第72条1項
「交通事故を起こした場合、運転者は負傷者の救護や警察への報告義務を負う」
道路交通法第117条の5第1項
救護義務違反に対し、5年以下の懲役または50万円以下の罰金。被害者の死傷が運転による場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金。
自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷罪)
7年以下の懲役または100万円以下の罰金。
危険運転致死傷罪(同法第2条・第3条)
無謀運転や飲酒運転を伴った場合、致死は1年以上の有期懲役〜最高20年、致傷は15年以下の懲役。
ひき逃げの刑事責任
ひき逃げを行った場合、以下のような刑罰が科される可能性があります。
救護義務違反(道路交通法第117条の5第1項)・・・5年以下の懲役または50万円以下の罰金、被害者の死傷が運転者の運転によるものであった場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金
被害者の救護を怠ること自体が重い犯罪とみなされます。
事故報告義務違反(道路交通法第72条)・・・3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
事故を警察に報告しなかった場合も処罰の対象となります。
過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)・・・7年以下の懲役または100万円以下の罰金
被害者が負傷または死亡した場合に適用されます。
危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条、第3条)・・・15年以下の懲役(死亡事故の場合は1年以上の有期懲役)
飲酒運転や無謀運転が伴う場合、さらに重い刑罰が科されることがあります。(致死:15年以下の懲役、致傷:12年以下の懲役)
ひき逃げの民事責任
ひき逃げを起こした場合、刑事罰とは別に、被害者に対する損害賠償責任(民事責任)が発生します。
治療費・慰謝料・休業損害の賠償
後遺障害が残った場合の逸失利益
死亡事故の場合の遺族への賠償
ひき逃げの場合でも、自賠責保険を通じて被害者への補償は可能です。加害者が無保険であっても、政府の「自動車損害賠償保障事業」によって救済される制度があります。
刑事裁判と民事請求の関係
ひき逃げ事件が発生すると、まずは刑事事件として警察・検察の捜査が進められ、加害者が起訴されれば刑事裁判が行われます。ここで加害者が有罪判決を受けたとしても、被害者が損害賠償を自動的に受け取れるわけではありません。
刑事裁判の目的は「加害者に対する刑罰」であり、被害者への補償は別の手続きとして「民事請求」を行う必要があります。具体的には以下のような流れになります。
• 刑事裁判:加害者の刑事責任を追及する。懲役・罰金など刑罰を決定。
• 民事請求:被害者が加害者に対して損害賠償を請求。治療費・休業損害・慰謝料などを求める。
刑事と民事は完全に別の手続きですが、刑事裁判での有罪判決や証拠は、民事裁判での立証に有利に働くことがあります。つまり、被害者は刑事事件の結果を待つだけでなく、民事請求の準備を並行して進めることが重要です。
被害者が取るべき対応
もしひき逃げの被害に遭った場合、次の対応が重要です。
1すぐに警察へ通報(110番)
2周囲の目撃者を探す
3ドライブレコーダー・防犯カメラ映像を確認
4病院で診断書を取得し、被害届を提出
5保険会社へ連絡し、補償の流れを確認
6弁護士に相談し、適正な損害賠償を請求
早期の行動が、補償の確保と加害者特定につながります。
被害者ができる損害賠償請求
被害者は加害者や保険会社に対して以下の損害を請求できます。
治療費:診察費、入院費、リハビリ費用
休業損害:休業中の収入減少分
慰謝料:精神的苦痛に対する賠償
逸失利益:後遺障害が残った場合の将来の収入減
死亡事故の損害賠償:葬儀費用、死亡慰謝料、遺族の逸失利益
加害者が特定できない場合の補償
加害者が逃走して見つからない場合でも、被害者救済の制度があります。
政府保障事業への請求
→ 自賠責保険と同水準の補償を受けられる。
自身の保険を利用
→ 人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険で補填できる場合がある。
後日加害者が判明した場合
→ 刑事責任の追及と併せて、民事上の損害賠償請求が可能。
加害者がとるべき対応 ひき逃げで疑われた場合の対応
万が一、自分がひき逃げで疑われた場合、次の対応が必要です。
身に覚えがある場合:すぐに警察に連絡し、誠実な対応を取る。
身に覚えがない場合:証拠を整理し、弁護士に相談。
警察の捜査に協力:無実を証明するためには、防犯カメラ映像やアリバイを提示することが重要。
被害者目線での弁護士に相談するメリット
ひき逃げの被害に遭った場合、弁護士に相談することで次のような具体的なメリットがあります。
後遺障害等級認定の申請・異議申立て
重い後遺障害が残った場合、適切な等級が認定されるかどうかで賠償額が大きく変わります。弁護士は医師の診断書の内容を精査し、必要な場合は異議申立てを行うこと等で適正な等級を得られるようサポートします。
保険会社との交渉
被害者が単独で交渉すると、保険会社から相場より低い金額を提示されるケースが少なくありません。弁護士が代理人として交渉することで、裁判所基準に沿った適正な金額を主張できます。
加害者目線での弁護士に相談するメリット
ひき逃げをしてしまった、あるいは疑われている加害者にとっても、弁護士に相談することは極めて重要です。刑事・民事の両面で責任を問われる可能性があるため、適切な対応を取らなければ処分が重くなる危険があります。
刑事事件への対応
取調べ
警察・検察の取調べにおいて不用意な発言をすると、後に不利に扱われることがあります。弁護士は適切な供述方法をアドバイスし、不利益を最小限に抑えます。
保釈請求や刑の減軽交渉
勾留された場合には保釈を申立てることができ、また被害者への賠償や謝罪を適切に行うことで、裁判において情状が考慮される可能性があります。
民事責任への対応
賠償の方法と範囲の整理
被害者に対する損害賠償は避けられませんが、弁護士が関与すれば賠償額の算定を適切に行い、示談の方向性を調整できます。
示談交渉の代理
被害者との直接交渉は感情的対立を招きやすいため、弁護士が間に入ることでスムーズな示談成立を目指せます。
社会生活への影響を最小限に
ひき逃げは重大な犯罪ですが、弁護士の助言のもとで早期に自首し、誠実に被害弁償を行うことで、刑罰や社会的影響を軽減できる余地があります。
まとめ
ひき逃げは重大な犯罪であり、刑事・民事の責任が厳しく追及されます。
被害者は適切な対応を行い、加害者は速やかに責任を果たすことが求められます。万が一、ひき逃げの加害者または被害者になってしまった場合は、弁護士に相談し、法的手続きを進めることが重要です。
P&M法律事務所では、交通事故に関する案件を数多く取り扱っています。是非一度、無料相談にお越し下さい。

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」